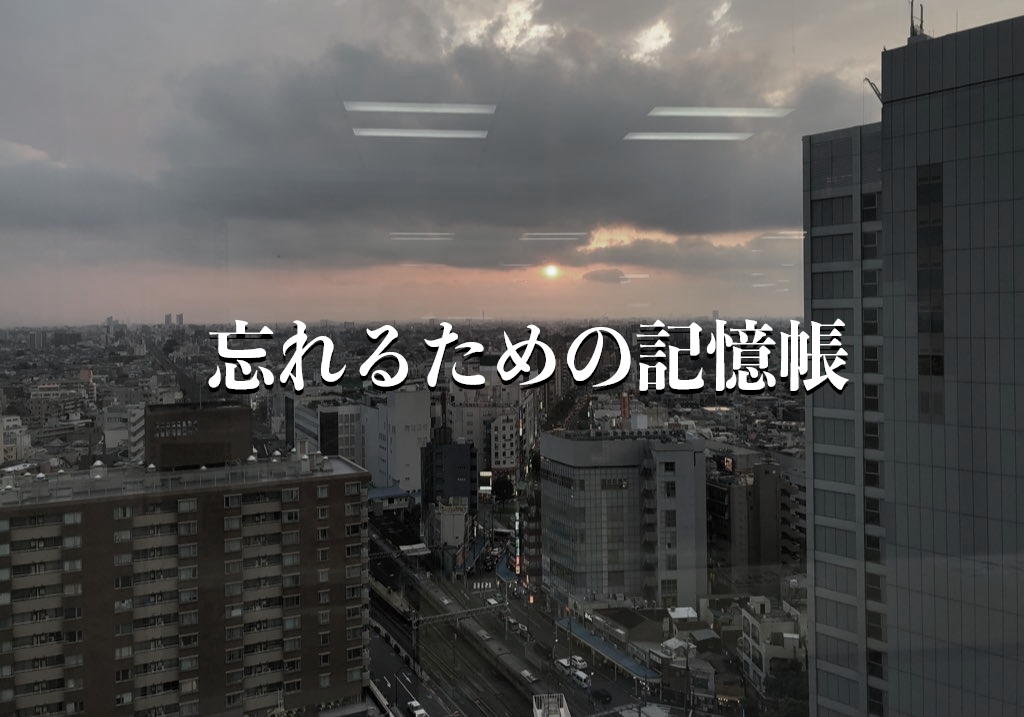月末は1月二度目の行政がらみの会議。
会議といっても1時間半しかないので、各所報告とごく簡単な質疑応答のみで終わり。
久しぶりの知り合いに出会い、おーっと歓声を上げる。
寒さが戻って、外に出るのも面倒ではあるのだが面倒以前に仕事が終わらず家に篭りきり。
映画も一体いつから観ていないのやら。
近所の映画館にいくのすら憚られる。
春までは黙々と仕事をするしかないか。
ハサウェイは映画館で見ないと絶対見ない気がする。
暗いから。
SNSでは皆ハサウェイについて語っている。
しかも演出など技術的なことについて。
画がすごいのは、そうなのだろうけど。
とにかく映画館へは行きたい。
昔、渋谷にあったパンテオンで映画の上映前にラッパーのIce-Tが挨拶したいといって突然スクリーンの前に登場するという出来事に遭遇したのだが、いったい何の映画だったのかタイトルが思い出せずにいた。
ほんとにIce-Tだったのか?も怪しい記憶になりつつあったが、キアヌリーブス主演の「JM」を観に行った時に違いないと先ほど分かった。
彼が確かに出演しているし、パンテオンで見た記憶がある。
戸田奈津子が通訳で付き添っていた。
しかし、その時来ていた客はあの広いパンテオンに数人か、せいぜい十数人だった。
たぶんIce-Tのことを知っていた人もほとんどおらず、突然のアナウンスにも鈍い反応だったと記憶している。
詳しくは覚えていないが丁寧に感謝を述べ、さらっと去っていった。
なんだか申し訳ない様ないたたまれない気分になった。
客入りの悪さは映画の出来を考えれば致し方ないと思う。
マトリックス以外はパッとしなかったキアヌもあの頃の微妙な扱いに比べたら随分と人気が定着したし、おたく的な文化もキワモノではなくなった。
おたくは表に出られるようになった代わりに、オタク文化のアジールとしての機能は縮小している気はする。
日に当たりすぎるのも気をつけないと逃げ場を失う。
寒さは和らいで欲しい。
ラナンキュラス・ラックスの苗を買ったが寒さが落ち着くまでは植えるのを待つ。
タグ: 映画
トリツカレ男を見たり【2025年12月07日】
もう終わってしまいそうだったので火曜日の朝に「トリツカレ男」を見にいった。
脚本がロロの三浦直之、ということで見ておきたかった映画。
ボーイミーツガールだったり歌だったり、三浦直之的な要素はあるが、それほどロロっぽさは感じられなかった。
原作を手堅くまとめる方向で仕事をしたということかもしれない。
お話は、かわいくて好ましい。
ビジュアルも日本のアニメっぽくなくて、地味に凝ったことをやっており良い。
キャラクターデザイン荒川真嗣、レイアウト三原三千夫
美術はPablo。
美術は写実一辺倒の昨今に挑戦するのは非常に難しい作風をしっかりやり切っていて素晴らしかった。
作画と美術を上手く溶け合わせた背景動画的なシーンも結構あって、しっかり計画された画面構成だったのだと思う。
カラースクリプトなども作られていたのかもしれない。
キャラに質感を入れていたのがすごく印象的で、自分でも挑戦してみたいと思っている技法なのだけど、取り入れるのは難しい。
キャラクター造形との相性もあると思うが、かなり上手く処理されていた様に思う。
どういう方法で作られていたのか知りたい。
べたっとした色面にならない様にという意図なのだと思うが、漫画的な造形にも応用できないだろうか。
ミュージカルとしてのつくりは、もう少し頑張って欲しかった。
アメリカ、ヨーロッパの作品と比べると前半はかなり見劣りする。
ラストは良かった。
ミュージカルを作るのは、かなり大変。
脚本をつくり、ストーリーボードの前に音楽をつくるか、後に作るかの選択。
音楽も完成した状態のものを貰って作るのはかなり難しいのでスケジュールの調整だけでもなかなか難しい。
リップシンクは日本のアニメは伝統的にかなり大雑把なので、慣れてる人もいないと思う。
リップシンクそれそのものがエンターテイメントだった、という話は細馬宏通「ミッキーマウスはなぜ口笛を吹くのか」に詳しい。
トリツカレ男はミュージカルファンを当てこんだ作品というわけでは無さそうだけど、誰か挑戦したら面白いと思う。
トリツカレ男を見たあと、今日しかないと安彦良和展に足を伸ばした。
松濤美術館なので、それほど点数はないかと思っていたけど予想より多く資料が展示されていた。
ガンダムの作監修正(修正用紙に書かれていたが直接描いた原画なのかも)やポスターの原画の類が見られたのは良かった。
キャラ表のポーズは皆何かしらキャラクター性が分かる様なポーズがつけられているものが多かった。
今は造形を伝えることを主眼とするので、あまりポーズがつけられることはない。
キャラ表は色彩設計の色指定表としても使われるので、あまり大きなポーズをつけると造形が分からず色が作れないということが起こるからだ。
昔は色数も少なかったので、多少ポーズをつけたところで問題にならなかったのだろうし、ポーズがあった方がキャラクター性がアニメーターに伝わると考えられていたのだと思う。
確かに表情集は作るけれどポーズ集までは作られない。
本当は、あった方が良いのかもしれないが現状は手が回っていない。
安彦さんの絵はシンプルで、とても上手いのだけれど今風ではないのだというのは直筆の絵を見てあらためて感じた。
今風ではないというのは批判ではない。
特に目の作り。
今は目の中だけで異常な数の塗り分けがある作品が少なくない。
安彦キャラは目だけで惹きつける様な作りではない。
立体を意識しすぎず、ディフォルメもあってまさに2.5次元。
今はとにかく3D的に考えられがちなのとは対照的だ。
漫画のカラー原稿はとても魅力的だった。
塗りがとても美しくて、絵の具の滲みが綺麗に作られていてため息が出る。
昔のポスターなどは厚塗りで普通のポスターカラーかアクリルガッシュの様なもので描いていたのだろうか。
図録をみると展示されていないものも多数あり、他の会場では出ていたのだろう。
松濤でも展示替えがある様なので、多少は見られるかもしれない。
最近、精神分析について調べている流れでR・D・レインの「好き好き大好き」を読んだ。
エヴァのネタ本の一つらしいが、確かに似ている台詞回しがあり、「精神防禦盾」などのワードも出てくる。
全体的には60年台の前衛芸術的な雰囲気で、実際影響も与えていたのだろう。
現代詩だが、脚本の様な対話が多く使われているのは著者が精神分析かだからか。
懐かしいアングラを感じた。
あとはグリーフケア関係の本をちょろちょろ読み始めていて島薗進「ともに悲嘆を生きる」は読み始めたばかりだが面白い。
ムスカリやアネモネの球根が植えられていない。
流石にそろそろ植えないとまずいが、急に寒くなって億劫だ。
仕事も地味に打ち合わせが多く、結局週末しかデスクワークは大きく進まない。
ストリーボード作成で学ぶ演出(のための準備)【05】イマジナリーの説明用認知科学理論・ナラトロジー
イマジナリーラインの根拠になるような認知科学の理論は無いのかと論文探したり本を漁っている。
・変化盲
・文脈効果
・対象の永続性(発達心理の中の言葉)
この辺の研究で何と無く説明はできそう。
直接的に映像に絡めた研究は英語でもあまり無さそう。
幾つかは、映像に絡めた論文もあるのでヒントにしたい。
変化盲は、これでほとんどイマジナリーラインの効果については理解できそうだが、これだけ詳しく説明した本や論文は見つからない。基本的なことすぎるのか…?
英語論文でロンドン大学?で認知科学と映像理解を絡めた研究をしている人がいるみたいだが、他はほとんど見つけられず。
流行りでない、ということか。
金子書房の「知覚・認知心理学」を購入。
比較的最近出た本で知りたいこと近辺について書いてある。
東京大学出版会から去年出た認知科学のシリーズは一個レイヤーが上というか、もう少し大まかな話が多くて使え無さそう。面白そうだし最近の知見がまとめられていそうなので読んでは見たいが。
映画理論講義修正を読み始めた。
ざっくりは使えそう。
古臭さはある。
講談社学術文庫から出ている橋本陽介「物語論 基礎と応用」をぱらっと読んだ。
前半は物語論(ナラとロジー)のざっくりした紹介で、これは使えそう。
後半は具体例で分析をしているが急にぼんやりとした感じで発見はない。
意外と最近出た本らしくシン・ゴジラや他のアニメも取り上げられていた。
やはりこの手の構造主義から派生した研究は60〜80年代あたりで概ね止まっている印象。だが、その後もポツポツと研究はある模様。
基本的には廃れ気味というか、流行ってない。金にならないというかとかと思われる。
嚆矢とされるジュネットの「物語のディスクール」は水声社で今でも買える様なので読んでみようかと思う。元は72年だから古い研究だなあ。
物語をめぐる様々な研究はあるようなのだけれど、記号学とか認知科学とかを絡めたものは少ない。
散発的なものを集めるには流石に時間と気力が足りない…。
物語論は基本、言葉についてなので映像に応用する場合は少し工夫が必要。
でも初心者に教えるためにはとても助けになりそう。
蓮見も多分このへんの詩学・物語論を軸にしていると思われるけど、昔読んで苦手だった印象が拭いきれず読む気が起こらない。
あとは浅沼圭司くらいか?
年末暇になったら、調べたい。
ストリーボード作成で学ぶ演出(のための準備)【04】「映画理論講義」
いろいろ探してみたけれど一般書で出ている映画理論の入門的な本は殆どなくて、2000年に勁草書房から出たこの本くらいしか見当たらなかった。今も新しい刷りで売り続けてるので参考に良さそう。
映画理論講義 –映像の理解と探究のために
著者:
ジャック・オーモン
アラン・ベルガラ
ミシェル・マリー
マルク・ヴェルネ
訳者:
武田 潔
目次:
序論 …………………………………………………………………………………. 3
I 映画文献の分類 ……………………………………………………………… 5
1 “一般的な”の出版物 ……………………………………………………. 6
2 映画狂のための書物 ……………………………………………………. 7
3 理論的著作 ……………………………………………………………… 8
II 映画理論の諸相 ……………………………………………………………. 10
1 “内発的”理論 …………………………………………………………. 10
2 記述的理論 …………………………………………………………….. 11
3 映画理論と文学 ……………………………………………………….. 11
4 映画理論と技術的実践 ………………………………………………… 12
5 映画理論の多様性 ……………………………………………………. 12
注 ……………………………………………………………………………… 15
第1章 視聴覚的表象としての映画 ………………………………………….. 19
I 映画的空間 ……………………………………………………………….. 21
II 奥行きの技巧 …………………………………………………………….. 32
1 遠近法 …………………………………………………………………. 32
2 被写界深度 ……………………………………………………………. 35
III ショットの概念 ……………………………………………………………. 41
IV 聴覚的表象としての映画 ………………………………………………… 48
1 経済的=技術的要因とその歴史 ……………………………………… 48
2 美的およびイデオロギー的要因 ……………………………………… 49
注 ……………………………………………………………………………. 55
第2章 モンタージュ …………………………………………………………… 61
I モンタージュの原理 ………………………………………………………. 63
1 モンタージュの対象 …………………………………………………… 67
(1) 映画作品の一部分(映画的連辞)でショットよりも
大きいもの …………………………………………………………. 67
(2) 映画作品の一部分でショットよりも小さいもの …………………. 68
(3) 映画作品の一部分でショットへの分割と(完全には)
一致しないもの …………………………………………………… 69
II モンタージュの機能 ……………………………………………………… 76
1 経験的アプローチ ……………………………………………………. 76
2 より体系的な記述 ……………………………………………………. 78
(1) 「創造的」モンタージュ ………………………………………….. 79
(2) 統辞的機能 ………………………………………………………. 80
(3) 意味的機能 ………………………………………………………. 80
(4) リズム的機能 …………………………………………………….. 82
(5) モンタージュの分類法 …………………………………………… 83
III モンタージュのイデオロギー …………………………………………… 83
1 アンドレ・バザンと「透明性」の映画 …………………………………. 84
(1) 「禁じられたモンタージュ」 ………………………………………. 85
(2) 透明性 ……………………………………………………………. 87
(3) つながりのためではないモンタージュの拒否 ………………….. 91
2 セルゲイ・エイゼンシュテインと「映画の弁証法」 …………………. 92
(1) 断片と衝突 ………………………………………………………. 97
(2) モンタージュの概念の拡張 …………………………………….. 97
(3) 観客に対する影響 ………………………………………………. 97
注 ………………………………………………………………………….. 100
第3章 映画と物語 …………………………………………………………… 105
I 物語映画 ………………………………………………………………… 107
1 映画と物語の出会い ………………………………………………… 107
2 非物語映画――境界を定めることの難しさ ………………………. 109
(1) 物語的/非物語的 …………………………………………….. 109
(2) 境界の基準 …………………………………………………….. 109
3 物語映画――研究の対象と目的 …………………………………… 111
(1) 研究の対象 …………………………………………………….. 113
(2) 研究の目的 …………………………………………………….. 113
II フィクション映画 ………………………………………………………… 115
1 あらゆる映画はフィクション映画である ……………………………. 119
2 指向対象の問題 …………………………………………………….. 119
3 物語言表、物語叙述、物語世界 …………………………………… 121
第4章 映画と言語活動 …………………………………………………….. 187
I 映画言語 ………………………………………………………………… 189
1 古くからある概念 ……………………………………………………. 190
2 初期の理論家たち ………………………………………………….. 192
3 「映画の文法」 ………………………………………………………. 197
4 映画における言語活動についての古典的理論 …………………… 201
(1) 伝統的な映画言語 …………………………………………….. 202
(2) 言語活動の消滅に向けて? …………………………………… 203
5 記号なき言語活動 ………………………………………………….. 206
II 映画――言語か言語活動か? ………………………………………… 209
1 映画的言語活動と言語 …………………………………………….. 210
(1) 言語の多様性と映画言語の一律性 …………………………… 211
(2) 言語活動、コミュニケーション、極の入れ換え ……………….. 214
(3) 映画言語の類同的なレヴェル ………………………………… 215
(4) 線状性と離散的単位の存在 ………………………………….. 216
はい、続きをお送りします:
(5) 映画における分節の問題 ………………………………………. 216
2 映画の理解可能性 ………………………………………………….. 218
(1) 知覚的類同性 ………………………………………………….. 219
(2) 「質料的希釈のコード」 ………………………………………… 221
(3) 映画特有の記述形式の形象 ………………………………….. 223
III 映画的言語活動の不均質性 ………………………………………….. 228
1 表現素材 …………………………………………………………….. 228
2 記号学におけるコードの概念 ……………………………………… 230
3 映画に固有なコード ……………………………………………….. 232
4 映画に非固有なコード …………………………………………….. 235
IV 映画作品のテクスト分析 ………………………………………………. 237
1 「言語活動と映画」における「映画作品のテクスト」という概念 …… 238
2 実例――D・W・グリフィスの『イントレランス』
におけるテクストのシステム ……………………………………… 240
3 文学の記号学におけるテクストの概念 ……………………………. 242
4 テクスト分析の抑制性と理論的射程 ………………………………. 248
(1) テクスト分析の主要な特徴 ……………………………………. 248
(2) テクスト分析における具体的な困難 …………………………… 251
注 ………………………………………………………………………….. 259
結論 ………………………………………………………………………….. 351
注 ……………………………………………………………………………. 359
参考文献(I、II)……………………………………………………………. 363
用語対照表 …………………………………………………………………. 403
索引(人名、映画題名、事項)…………………………………………….. 417
訳者あとがき ……………………………………………………………….. 453
原書は初版が1983年、改訂が94年らしいので30年くらい前にフランスで出版されたらしい。
私が学生の頃なので参考で扱ってる映画も古いがまあ仕方ない。
少し読んでみたが凄く抽象的な部分はあるけど、使えそう。
映画評論はずいぶん沢山出ているし理論的な更新みたいなものは無いのか?と思うけど無いのかもしれない。
渡邊大輔が言ってることなんかは新しいと思うけど、入門としては必要ないのか…いやそうでもないような。
YouTubeはじめ映像メディアは様々広がっているので本当は更新されて良さそうだが。
学校などでは、どういう本を教科書で使っているのだろうか?
私が見つけられないだけで、良い本があるのかもしれない。
フィルムアート社から出ている入門書的なものは実務的だけど理論が薄そう。パラパラめくってみただけなんでわからないが。
認知科学とかも随分進んでいるので、その辺りを引いたものもありそうなものなのだが。
その辺を調べ出すと無限に時間がかかりそうなので躊躇してしまうが、多少はやらないとダメそうだ。
そのあたりは良さげな本のあたりがついてるので。
私が学生の時は、ほしのあきら「フィルムメイキング」を使ってた。本人が講師だからだが。
エイゼンシュタインの理論などは、ぱらぱら読んだけど流石に嘘でしょみたいな部分も多くて今素朴には読めない。
「映画理論講義」はそのへんもざっくり整理してあるみたい。とにかくざっくりでも読まないとなぁ…。
実務的なものは他にも良さげな本があるので、参考にしようと思う。最近の学生はそういうのを読んでるのかもしれない。
映画記号論的なものはだいぶ前に死滅してしまったようで、理論書は流行らなくなったのかも。
私が教わった浅沼圭二で終わってるぽい。
映画分析的な本は色々ある。
苦手な蓮實重彦もめくってみるべきなのかもしれないが。
私のやろうとしてることも、どちらかというと実務寄りだし。
久しぶりに更新。
嘔吐・シビルウォー【2025年02月09日】
結局うちの辺りは雪は降らずで助かった。
しかし風が強いので寒さが沁みる。
週明けからは少し暖かくなるという予報だが…。
久しぶりに腰痛が出ているので散歩に行きたい(少し運動しないと治らない)のだが、寒くて外に出る気力が全く湧かない。
今日は植物を買いに行くという理由をつけて久しぶりに少し歩いた。
仕事は終わらないし、打ち合わせか買い物でもなければ外に出るきっかけが無いので何か歩く口実を作らないとまずい。
忙しいと椅子で居眠りしたり、うっかり床で横になったりで腰をやってしまうことは良く有って、気をつけていても、猫に構え構えとせがまれて遊んでるうちにうっかり床で寝落ちて後悔したり。この世の終わりの様な声を出して廊下で鳴かれては集中できない。
新しい文芸誌GOATに載っていた小川哲の「嘔吐」を読んで爆笑した。
女性小説家を推してるファンの炎上騒動をネタにしてSNSあるある言説が書かれていて笑うと同時に頭がを抱える。
ネット上のライトで真面目に読むに足らない批判だが微妙に痛いところを突いてくる感じなどがうまく再現されていて苦笑。
ラストの切り捨て方は笑えるのだが、現実はああバッサリといかないか。
筒井康隆の「大いなる助走」が読み返したくなった。
シビル・ウォーアメリカ最後の日を仕事しながら見た。
映像はとても良くできている。
戦闘シーン、残虐シーンは割とストレートに血みどろでネット上に溢れかえる残虐シーンを見慣れている人間にも説得力を感じさせる。
しかし、肝心なことは何も言ってない言わない感が強すぎて虚無。
ジャーナリストが主役なのだが、肝心の内戦がどうして行われているのかという事には全く触れないので沢山描かれる死も娯楽的な要請以上のものは無い。
最後まで重要なことは何も言わないまま見せ切る脚本力は大したものなのだが仏作って魂入れずの典型に見える。
マウリポリの20日間の方が残虐シーンはあまり無いもののよほど恐ろしい。
仕事しながら起きていたのでトランプ大統領と石破首相の会見を見ようと思っていたら少し寝落ちしている間に終わっていた。
石破氏が68でトランプが78。元気だなあ。
仕事のトラブル諸々は何とかなりそう。
劇伴ラフが出来た。良い感じである。
アイカツ!劇場版再映【2024年11月26日】
そういえば、劇場版アイカツ!が今週末から再上映される。
もう劇場版初上映から10年だそうで、早いものだなぁと感慨に耽ってしまう。
土曜日には池袋のグランドシネマサンシャインで諸星すみれちゃんと舞台挨拶がある。
劇場版は結構たくさんイベントをやっていろんなことを喋ったので何を話そうかと考えている。
運営からの質問アイデアはあるものの何か話してないような思い出があったかな…と。
10年で随分いろんなことを忘れているので(何を話したかも忘れつつある)繰言のようなつまらない話にならないようにしたいものだが。
すみれちゃんが一緒にいるので、殆どの人は彼女を見るだけでも来た価値はあろうと思うのが救いである。
アイカツ!は定期的に昔を思い出す機会が訪れるので比較的に思い出せることは多いと思う。
当時、プロモーションで結構駆り出されて色んな事をさせられた記憶がある。
今も監督はプロモーションに寄与出来ているのだろうか…と甚だ疑問なことはあるのだが、体験としては面白かった。
今思えば、最初の頃は舞台挨拶も緊張していた。
初めての舞台挨拶は豊洲の劇場だったように思うが、控室では全く緊張を感じていなかったのだけれど、客前に出て急激に緊張したのを覚えている。
そりゃあ、結構大きなスクリーンだったし新人監督としては仕方ないだろう。
笑いの一つも取ってやろうと思っていたのだが、ジョニー役の保村さんがクルリと回って(控室では絶対パフォーマンスはやらないとか言っていた気がするが)華麗に笑いを取ったのを横目に見て感心するばかりだった。
大阪でも舞台挨拶とテレビ用のショートのインタビューとか。
告知を噛まずに言うのがいかに難しいか思い知った思い出がある。
コメンタリーなどのトークショーも凄くたくさんやった気がする。
殆ど私が司会進行のような形で90分のコメンタリー上映をやった時は流石に少し喋りが上手くなったような気分になれた。(大したこたぁないのだが)
何かの(アフレコだったか?)イベント終わりで予定していなかったスタッフが沢山参加してくれて助かった。
ただ喋るだけでも90分は非常に喉が疲れて大変なのだ。
そもそも、喋る内容などをある程度は考えておけば少しは上手く話せるのに、打ち上げの挨拶などですらその場の思いつきで喋ってしまう。
最近は良くも悪くも場慣れして緊張することもあまり無くなって上手くはないがリラックスして話せるので(トチっても気にしない)聞いてる方も楽しく聞いてもらえてると思っている。
一人でカメラに向かって話すようなコメント撮り的なものはいまだに苦手で、客前で話す方が気楽だ。
確か、バルト9でやった舞台挨拶の後、近くの交差点でファンの男の子が待っていてサインを求められた。
サインなど求められたことが無かったので普通に名前を書いただけだった。
アイカツ!に勇気づけられました、ありがとうございました的な事を言ってくれたのだが、ありがとうはこちらのセリフである。
この仕事をしていて、まさか誰かに感謝の言葉を貰う時が来ようなどとは思いもしていなかった。
子供向けであるし、素朴に面白ければ良いというつもりで作っていた作品なので、自分の想像を超えた反応に戸惑いというか申し訳ないような気分になったこともあるのだが、(何度も書いた気がするが)貴重なありがたい経験をさせてもらった。
劇場版は自分で絵コンテを描いているわけでもないし、演出もやっていないし、本当に周りのいろんな人の力で出来た作品だった。
自分の仕事のほとんどは、加藤さんとの脚本作りの中に集約されている。
当時の自分に出来ることや思いは全て投じて作った作品ではあるので、それが今だに多少なりとも人の心に残っているというのは嬉しい限りである。
久しぶりの劇場での上映なので、お時間のある方は是非見てほしい。
会える方は、土曜日に劇場で会いましょう。
暑さが身に染みる【2024年07月07日】
急激な暑さが襲ってきた今日この頃。
少し外に出ただけで、くらくらと眩暈がしてくる。
植物も日にあたりすぎると弱ってしまうものは日陰で過ごさせたりしなければならない。
もう日本は亜熱帯のようだ。
滑り込みでオッペンハイマーを見た。
都内の劇場だともう終わりかけだが新宿東宝のIMAXでやっていたので仕事帰りに見に行った。
仕事帰りに3時間の映画は、ちとしんどいな…と思っていたが意外と集中して見られた。
音響のイメージがかなり重要な作品だったのでIMAXで見られたことはラッキーだった。
原爆作成の過程から完成辺りは、微妙な気分になるのだが、人間の奇妙さのようなものをオッペンハイマーを通して良く描いている。
単なるドキュメンタリー的ではない手法で人間の内面と表層を表現していて面白かった。
史実的なところはダイジェスト的な作りになっているので、本などを読まないと良くわからないことも多々ある。
反戦映画という訳でもなく、かなり変わった趣向の映画だと思った。
最近、臨床心理の本を読んでいるせいか子供の頃のことをポロポロ思い出したり考えたりするのだが、それとも重なるような映画だ。
映画を見た以外は仕事ばかりで書けるようなこともない。
一つあった、アイカツ!のスタッフだった人と今やっている現場で顔を合わせた。
元気にやっているのがわかるのは嬉しい。
もうしばらく仕事漬けなのは致し方ない。
散髪【2024年03月28日】
髪を切りすっきり。ひさしぶり。
美容師のお兄さんにビールを献上。大変喜んでくれた。
最近はお酒が飲めず大量に余っている。
体調は上向いてはいるものの、まだしばらくお酒は控えるつもり。
3月も後半で少しづつ暖かくなってきているのでありがたい。
寒い時期は何かしら体調が崩れがちなのは歳のせいで致し方ないのだろう。
シラスで山﨑孝明という心理療法士(どうも定義が難しいらしい)の精神分析についての講義をみる。面白かった。
エヴァは精神分析の用語が沢山引用されているようだが山﨑氏はエヴァをきっかけに精神分析にはまったらしい。
フロイトは興味ありつつ手が出ずにいたのだが、藤山直樹の集中講義・精神分析は買ってあったので、ざっとでも読んでみよう。
山﨑氏の精神分析は文学という言葉が刺さった。
以前は精神科の診療はカウンセリングも一体なのだと勘違いしていたが山﨑氏の「精神分析の歩き方」で随分違うことを知る。精神科の医療は基本的に物理。
カウンセリングも精神分析も現状は医療行為ではなく保険が効かないので高い。
そもそも精神分析を医療行為ではないと考える精神分析家(日本に数人しかいない)もいるようだ。
カウンセリング、精神分析的心理療法は精神分析を実際の臨床治療に応用するというものだが、その内実の腑分けは難しいので山﨑氏の本など読まないとわからない。
心理療法をやっている人たちにも良し悪氏があるようなのだが、使う側にとってはかなり見えずらい世界。
医療としての精神分析はともかく、物語の中のキャラクターを考える上で精神分析は非常に有用そうだ。
ハリウッドの脚本だと当たり前のように精神分析の考え方が使われているとも聞くが実際はどうなのだろう。
オッペンハイマーは見に行こうかと思っている。
ノーランの映画は長くてラストの方でいつもトイレに行きたくなるのだが、頑張ろう……。
今回も3時間あるとか。
今日は会議だ。
トップガン【2024年02月03日】
SNSは原作とその映像化についての騒動で持ちきりで、私も言いたいことがないではないが基本的に今回のことに限らず原作と映像化についての揉め事はマネジメントや企画側の問題だ。基本的には商売の問題であって芸術的な問題ではない、と概ねの業界人は考えているだろうと思う。私も人の経験談や自分の経験を踏まえてもそう思う。
とはいえ、商売と芸術を厳密分けて考えることは難しいのだけれど。
個別の事情も分からなすぎるが誰かの自死という結末はあまりにも悲しいので何らかの大きな改善が必要だろう。
さて、トップガンを映画館で見たのでメモ。
公開当時は映画館で見た記憶がないので初めてスクリーンで見たのかもしれない。
何度か見ているのに、やはり映画館で見ると発見がある。
こんなシーンあったけ?とか、いい加減に見ていただけかもしれないけど。
トム・クルーズのほっぺたが、ぽちゃぽちゃ。86年公開だから撮影当時は22、3歳だろうか。
ヒロインの女教官シャーロット・”チャーリー”・ブラックウッド役のケリー・マクギリスとは実年齢4歳差。映画だともう少し差がある様にも見えて、それらしい配役。
映像はリマスターのおかげか概ね綺麗に感じた。
色味はコクピットの内部など特撮が絡んでいる様な部分は少し気になるくらい。
若い人の目にどう映るか分からないけど、青春物語としてよく出来た脚本になっているのが印象的だった。
まず前半は少し無鉄砲な若造がチャンスを掴んで調子に乗っていく、後半は大きな挫折を交えながら前半の展開を反転させた様なイメージ。
最初はマーヴェリックに追いかけられるチャーリーが車で追いかけてマーヴェリックを捕まえるシーンは秀逸。
恋愛、父の死の謎、友人を亡くしての挫折、そして再起、そう長くはない映画で、起きた出来事、謎の決着はほとんど着けていて娯楽作品としては素晴らしい作り。
友人を亡くしたところで、ライバルのアイスが短い悔やみをマーヴェリックに言うなど細かな気配りで、あまり嫌な印象のキャラクターが残らないようにしている。
時代の気分を色濃く切り取っていてヒット映画というものはそういうものなのだなとも思う。
歌物以外の劇伴も良いのだけれど、どうも売ってないみたいで残念。
最近見たもの【2024年01月14日】
Netflixで碧眼 Blue eye Samuraiを見た。
なかなか面白かった。
3Dでフランスの会社がつくっているらしい。
エログロ・アクション系。
アクションがとにかく凝っている。血はたくさん、指も腕も足も切られて良く飛ぶ。
エロもちゃんとエロい。
裸のモデルはポリゴン数が多いようには見えないが柔らかく見せている。
セリフがきちんとエロティックである。日本のアニメではあまり見たことがない。
世界観はありそうで無い幕末のパラレルワールド的な架空の日本。しかし良く風俗を調べているようで嘘のつき方が白けない。
監督は女性の凄腕アニメーターらしく芝居は本当に良い。
モブのモデルなどもかなりいろんな種類を作り込んでいるように見える。物量的にも相当大変だったのでは無いかと思うが使い回しなどが上手いのかもしれない。
シナリオは序盤はとても引っ張られる。途中、母親のエピソードで主人公の主人公の行動原理がぼやけたところや、後半に行くにつれポリコレ的な目配せが目立つようになって仕方ないところはわかるが失速感を感じる。が、概ね良くできている。
日本だと川尻さんの作品のようなテイスト。
日本でもまたこういうのを作れる人が出てくると良いが…。
あとはアマプラでスピルバーグのフェイブルマン。
こちらも面白かった。
スピルバーグの自伝的な作品。
懐かしいカメラが沢山出てくるので、そこだけでも堪能できる。
ボレックスは8ミリのカメラも作ってたのか?分からないのだけど、16ミリのカメラは学生時代使っていて懐かしかった。
いい感じに屈折した青春物語になっていて、単なる映画少年のサクセスストーリーではない。
恋愛が大人にとっても子供にとっても人生を救ったり落っことしたりするように、映画作りも人生を救ったり落っことしたりするという当たり前のことを温かく描いている。
映画館で観たかった。