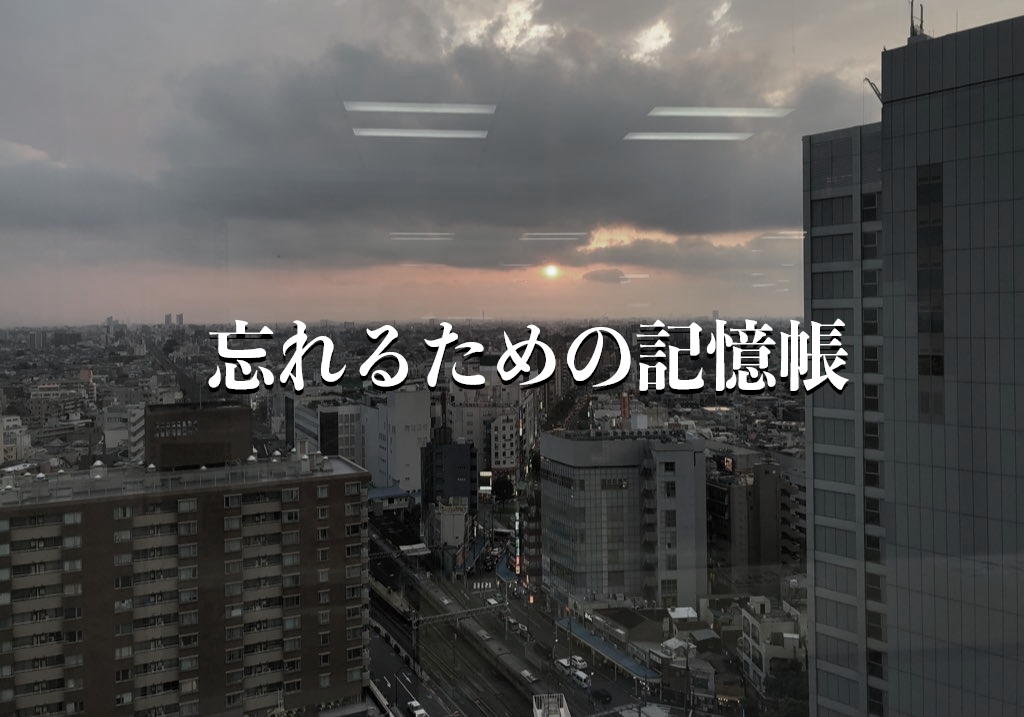おとなりに銀河は実写版とアニメ版と同時期の放送となったわけだが、実写版は一足早く終了。
まだ全部見られていないものの、自分の関わったアニメ版とのアレンジの違いなんかも楽しめてとても面白かった。
少し前にアイカツプラネット!で実写の現場を見せてもらったので、手がかかっているところとかアレンジの理由なんかもある程度分かって、作り手目線でも楽しめた。
装飾という部署の仕事ぶりがとても素晴らしかったのが個人的なツボ。
私も仕事で関わるまではよく分かっていなかったのだが、美術と呼ばれる部署は基本的にはセットなんかの設計だけ。実際に作るのは大道具さんで、部屋の中に置いてあるものとか役者が手荷物以外の全てのものは装飾と呼ばれる仕事をする人たちが作る。
作ると言っても1から10まで手作りというわけではなくて既製品と作り物を組み合わせて作品の世界を作っていく。
夜ドラのおとなりに銀河の場合だったら、キッチンの作り込みが素晴らしいなと思った。映る回数が多いので手をかけたということではあると思うけど、生活感の溢れる感じで物が置かれていて、あの感じをアニメで作るのは相当に難しい。
アニメの場合は、ありとあらゆるものを描かなければいけないので、ごちゃっと物がたくさんある空間はとてもカロリーが高い。実写でも、その手間は実は同じではあるのだけど、アニメの方が仕事のカロリー的には高くなってしまう気がする。
なので、ああいう空間作りを見ると羨ましいなと思う。
アニメの得意なのは、既製品にないものを作れること。
実写版では、やはり漫画の中のキッチンとは大分違う形の部屋になっていたが、アニメはほぼそのまま再現している。
実写ドラマで同じことをやろうとすると、まず部屋のセットを作って漫画に合わせて調度品を全部作って……こうなると仕事のカロリーが一気に跳ね上がり、予算と時間がないとちょっと無理みたいな話になる。
アニメは、そういうフルスクラッチな作業は比較的得意だ。
でも、実写もアニメも作業の物量が多くなれば大変なのは同じで重なる部分も多い。
実写もアニメも得意なところ不得意なところがあって、制作陣は最大限自分たちの使う表現方法の良さを活かして作っていくので、そんなことを気にしながら見るとまた違った楽しみ方ができるかもしれない。
「おとなりに銀河」アニメは1話が無料公開中なのでお時間ある方は是非。