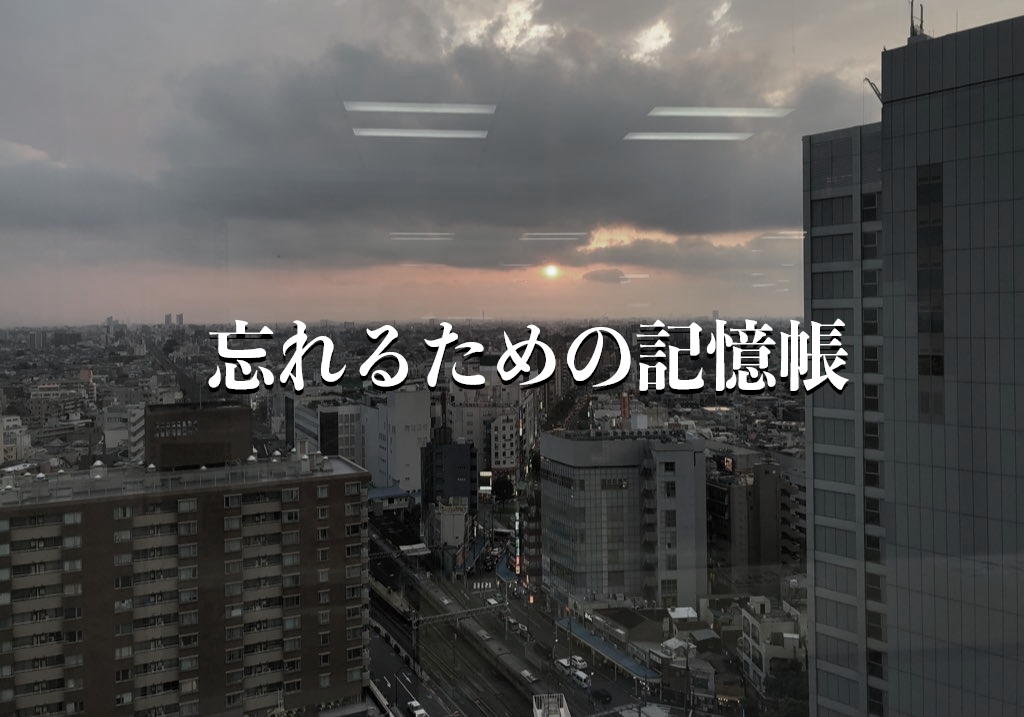2023年1月20日、今週の金曜から映画『アイカツ!10th Story 〜未来へのSTAR WAY〜』(タイトル間違っとるかもしれん)が公開になる。
先日、初号試写というやつをやった。
初号ってなんだよ、っという御仁に少し説明するとひと昔前まで映画は合成樹脂の透明なフィルムに映像を焼き付けて後ろから光を当ててスクリーンに映写していたのだ。
テストで焼いたフィルムを0号といって、調整を経てお客さんに見せられる状態で焼かれたフィルムを「初号フィルム」と言っていたのである。
フィルムを焼く、という表現も若い人には甚だ分かりにくいと思うが割愛。
今はDCPというデータで上映されているので、お客さんに見せられる状態のDCPの映像を初めてスクリーンで関係者が見る事を初号試写と呼んでいる。
出来上がった作品は何度か見ているので、さすがに落ち着いて見られたのだが、集まった関係者の懐かしい顔を見ていてグッと込み上げるものがあった。
放映開始から10年経ってるので、立ち上げからアイカツ!のプロジェクトに関わっていた人は殆どいない。
私もアニメの企画が始動を始めてから入ったので、本当の立ち上げから関わってるのは加藤陽一くん位かもしれない。
とはいえ私もほぼ立ち上げメンバーで、アニメの現場で立ち上げに関わっていた人は今アイカツチームには私以外いない。
試写では、そんな立ち上げ当時のメンバーが結構集まってくれた。
作品に直接関わってくれている人ももちろんいるが、もう離れている人ともちらほら来てくれていて、とても嬉しかった。
MONACAの作曲家・帆足くんとは何年ぶりかで会えて思わずハグしてしまった。
アイカツ!的、作詞家・御三家の辻さん只野さん、こだまさんも来てくれていた。
只野さんは、試写の後ずいぶん長い事ロビーに残って話し込んでいて帰りもご一緒してしばらく話し込んだ。
只野さんは20年近く続いているプリキュアにアイカツ!より長く関わっているので、色々話して励みになった。
関係者は、監督にとっては最も先に反応してくれる観客だ。
意外と関係者の反応はビビットなので、見せる前はドキドキする。
試写の後の皆んなの反応を見て少し安心できた。
これで観客・ファンに見せられる、と思えるようにはなったのだが、まだ怖い気もする。
作品は終わって仕舞えば完全に観客のものだ。
観客の心の中に残っているものが全てだ。
アイカツが終わったときは娘を送り出した様な気分になったのを憶えている。
今回の作品は、一旦、観客の手に渡したものをまた返して貰って作った様なものなので非常に緊張している。
ただただ楽しんでくれる事を願うばかりだ。
今回の映画は完全に昔見てくれていた人に振り切って作っている。
当時、アイカツ!がメインターゲットととして想定していたのは7〜9歳の女の子。今、高校卒業したかしないか位の年齢の人たちだが、その世代の人たちに向けて作った。
なので卒業をテーマとして取り上げてある。
10年経つと当時ファンだった子がスタッフとして働いていたり、演者として関わっていたりもする。
私もアイカツ!に関われた事で色々な経験をさせて貰った。
今度の映画はそういう色々への感謝の気持ちも込めたつもりだ。
いや…大仰な内容ではないのだけれど、むしろこんな話で大丈夫なのか?といまだに心配だけれど、オールドファンは楽しんでくれるのではないかと思っている。
なにはともあれ、もうすぐ公開である。
この映画をきっかけに、しばらくの間ファンも関係者もアイカツ!10周年を楽しんでくれたら、こんなに嬉しいことはない。