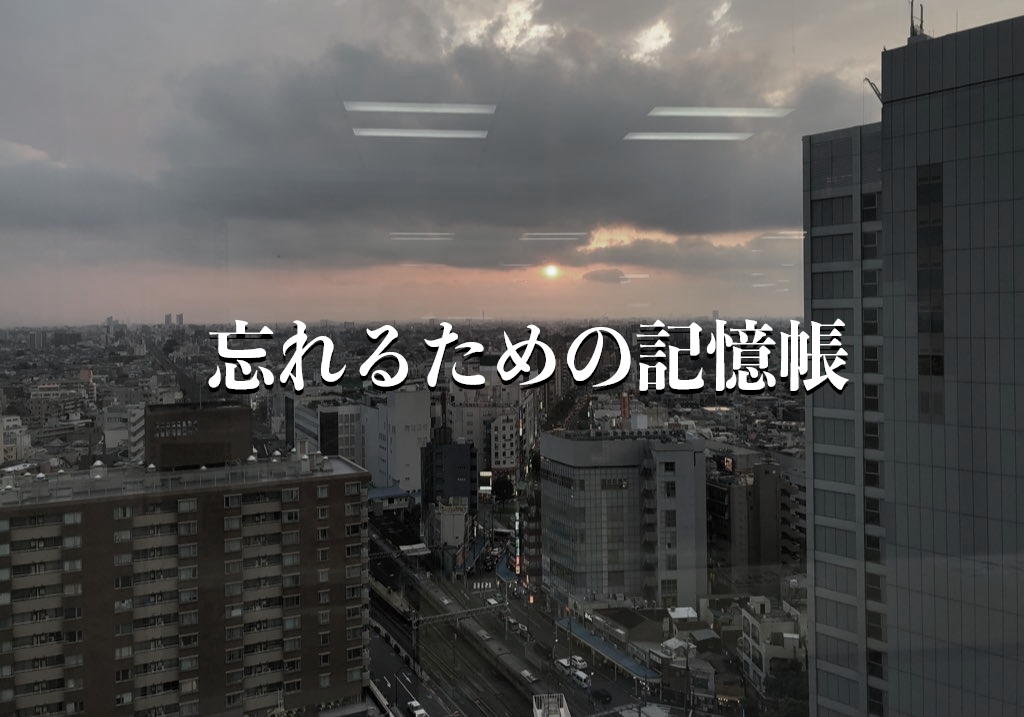ジブリが日テレの子会社になったそうで。今までは子会社じゃなかったのか…と思うほど近い関係だという印象だった。
宮崎さんも、まだ作る意欲があるようだけど、さりとて体力は衰えていくばかりだろうと思うと大きな会社と組みつつ今後を考えるのは自然ななりゆきなのだろう。
で、子会社になりましたよという鈴木敏夫さんの記者会見の記事を読んでいると、後継者作りに悉く失敗したというようなことを仰られていた。
はて、そう言われると確かにジブリの看板を背負って作り続けると言えるクリエーターは居ないのかもしれない。宮崎吾朗さんは違うのかな?
後継者は出なかったのかもしれないが、若い人を育てるのに失敗したのかというとそんなことは全くない。
ジブリで育ってジブリを出て活躍している方は大勢いるわけで。
後継者作りにことごとく失敗した、という鈴木さんの弁は少し大雑把なのではなかろうか。
私もジブリが演出を育てようと始めた塾の出身。
私が入った塾は高畑勲さんが塾長をしていた。
入って早々、高畑さんはジブリで育とうとかはあまり考えない方が良いと思う、というような事を言っていてたと思う。
さもありなん、ジブリの作品の予算は新人の演出家が背負える様な規模ではない。
ジブリに限らず、会社が新人のクリエーターを育てるというのは大変でなかなか上手くいかない。
育ったと思ったら出て行ってしまったり、リスクも大きかった。
とはいえ、継続的に作品を作っている会社からは、それなりに人が育っていると思う。
回遊魚みたいに色んな現場を回っていて、ひと所になかなか居付いていないと思うけど。
京都アニメーションなんかは比較的に人を育てるのに成功しているのじゃなかろうと思うし、多分少しづつ会社に居続けてくれるようなクリエーターを作る試みは広がっていて成功しつつあるところもあるよいに思う。
鈴木さんの記者会見ではテレビシリーズの制作も視野に入れているというような発言もあったし、上手くいけば新しい人材が育っていくのだろう。
ブランドを維持するためには大きなチャレンジが必要なのだろうと思うけど、成功を祈りたい。