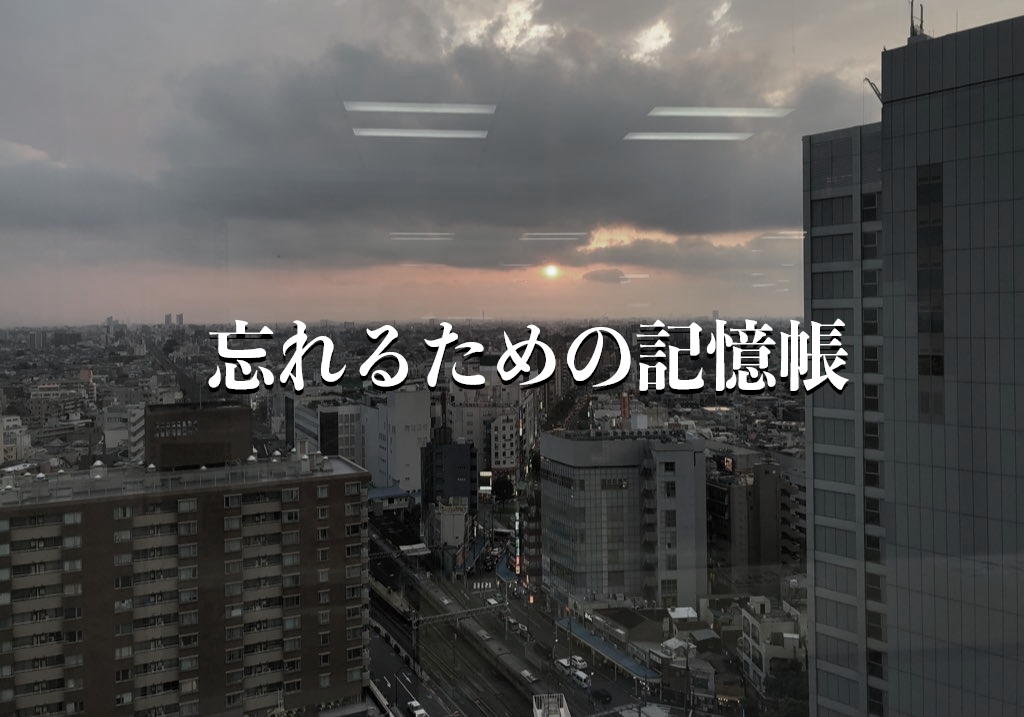ゆるりと仕事再開。
しばらくは絵コンテマンとして活動することになりそう。
全く知らない監督の仕事はあまり来ないものではあるのだが、自分ではない人にコンテを提供するときはどういうスタイルがいいのかなという探りを入れたりしてなるべく監督のスタイルに合う様に考える。
とはいえ、他人と同じものは絶対に描けない。
絵コンテだけの仕事を請け負う様になってずいぶん経つけれど、真似しずらい理解しずらい微妙な表現はオーソドックスに作る様にしている。
絵コンテにオーソドックスも何もあるのか、と言う向きもあるかもしれないが有る。
キャラクターの捉え方(人物造形)お話の捉え方が極端に間違っていなければ、あとは基本的な映像文法を守ったあげるだけで監督は絵コンテの修正が圧倒的に楽になる、と経験的には思う。
キャラクターとかお話の理解を除くと、技術的な違いが大きく出る部分は3つある。
一つはイマジナリーラインの作り方。
一つはカメラの高さ。
一つは話題の対象を写すかどうか。
一番面白いなあと思うのは、話題の対象を写すかどうか、のところだと思う。
話題の対象とは何かというと、例えば何か会話をしている人物が二人いたとして、そのうちのしゃべっている人を写すかどうかみたいな事だ。
そんなの普通しゃべっている人がいたら、その人を写すでしょと思うかもしれないが意外とそうでもない。
しゃべっている人の話を聞いている相手はどんな顔をして聞いているのか、という事が重要な場合はその表情を写すということがあるが、この場合は一般的な話題の対象を写しているという認識で良いと思う。
例えば、長いしゃべりの時に窓を写すみたいな演出はアニメでは非常に良くあるのだが、私はこれは話題の対象を写さない演出に分類する。
これが悪いというわけではないのだが、外す必要がないのに外している場合や、外してはいけないのに外してくる人もいて、さて何故だろうかと考える事が時々ある。
話し手の表情を想像させる、セリフに集中させる、それぞれに色々理由があってやっていることだろうと思うのだけれど憧れた作品からの影響というのも強くあるのじゃないか。
エヴァ以降といって良いかと思うのだけれど、深夜アニメなどで対象との向き合いが少し変わっている様な変わった演出が流行っていたと思う。
その影響を強く受けている人は結構いて、その事に自覚的ではない人もおり、自覚的でないと作品によっては全然合わない場合がある。
最近の主流は割とオーソドックスなスタイルに戻っているという印象を私は持っていてオーソドックスはやはり出来た方が良いと思う。
オーソドックスなものは見飽きてつまらないみたいな時代は終わってしまってオーソドックスなものしか見られないような時代になってしまった気もして、それはそれでどうなのよと思うけど伝統の中で育まれた王道なスタイル、方法論はやっぱり重要。
大作映画も基本的にはオーソドックなスタイルに則って造られている様に見受けられる。
まあしかしオーソドックスが体系的に教えられている場所、というのが今はハッキリと存在していないと思うので伝統が教えられる場所があるといいね。
ハッキリ教えられてないのに、やっぱり存在する伝統問いのも凄いもんだと思うが。