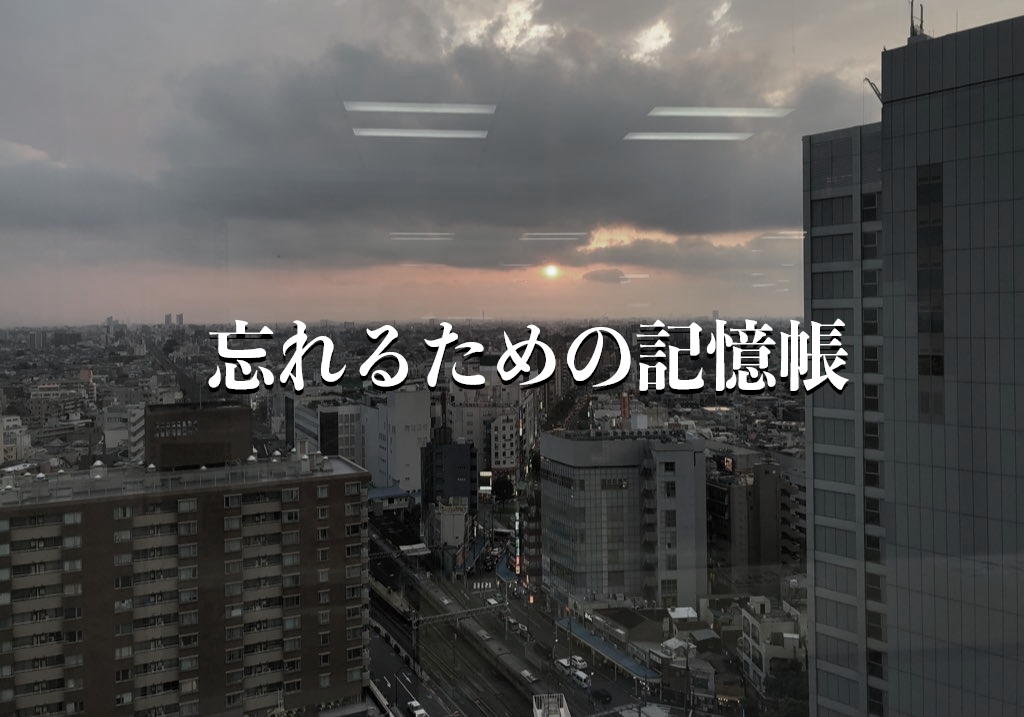仕事が終わらん。
久しぶりに原画チェックをしている。
顔が崩れている…からちょこちょこと直しの指示を入れたりは仕方ないと思えるのだが、第2原画を請け負う人たちは多分コンテも読まず、レイアウトに入っている演出指示も読まずに作業しているモンだから指示(簡単な事も)対応が抜けていたり、誰が誰を見ているかなどを理解せずに描いている。
第2原画どころか、作画監督も演出指示読んでないんじゃないかと思う。
連続したカットでも違う人に発注したりしているし、引き絵のカットは描き手が見つからないという理由でアップだけ先に上がってくるので、繋がりを確認できない。
レイアウトで合わせてあっても、つながりで作業者が違うと作業者自身が他の素材を見られないので前後の繋がりの確認ができない。
恐ろしく効率が悪い。
これは今の仕事に限ったことではなく、数年前から中規模作品は全てこんな感じ。
賽の河原で石を積んでいる気分。
少しづつ暖かくなってきた。
ラナンキュラス・ラックスの苗を買ってあったので大きめの鉢に植えた。
去年コガネムシの幼虫に根を食われたプレクトランサスが寒さで完全にやられて枯れたので代わりに植えた。
ラックスは強いので楽しみ。
花の期間はそう長くはないのかもしれないが。
金魚草はよく咲いている。
ストックとプリムラも。ネメシアが花芽がついているが何故か咲かず。
ビオラ。パンジーはこれから大きくなると思うが鉢が小さいかも…。
この間降った雪のせいか、スーパーアリッサムの調子が悪い、というか多分枯れている。
寒さは強いはずなのだけれど。
花が咲かなかったサルビアも枯れた。
映画館へ行きたいが全く余裕がない。
ライブなども行きたいがチケットを取る気力が湧かない。
うーん、なんか行くか。
本だけ地味に読んでいる。