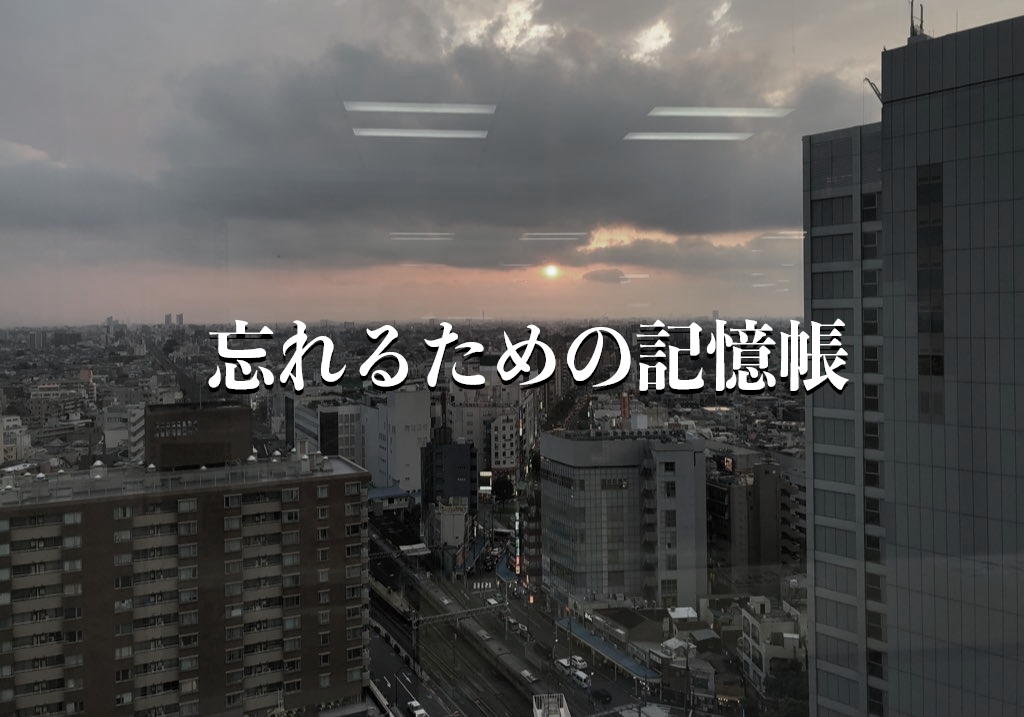土曜の朝はあまり雪は降らず、軒下に避難した植物たちを元に戻そうかとおもっていたけれど、面倒なのでそのままにしていたら今朝はしっかり積もっていた。
結局、軒下の鉢にも結構積もってしまったが大丈夫だろうか。
本当に寒さに弱いものは避けていたはず。
期日前投票など行く暇はないので、雪の中を歩いて投票所に行ったが、あれだけ積もっていると老人歩くのはしんどいだろう。
最近の制作はとにかく監督に確認を取りたがる(そう教育されているのだと思う)
監督に確認をいちいち確認とっていたら制作が停滞する。
昔は好き勝手にやりたいという人も多かったし、わりに各話のスタッフに自由が許されていたので、さすがにしくじると怒られそうな案件以外はなるべく監督を通さないという現場も多かった。
最近は作品の作りが全体に几帳面になってしまったのと、12、3本の短いシリーズが多くなってしまったため各話のスタッフが作風や全体像を把握しきれず監督に聞かないと怖くて進められないというのもわかる。
原作などクライアントの意向を監督を通して確認するようなことも多い。
それにしても、同じ様なことを何度も聞かれたりするのはいかがなものかとは思う。
監督なんて居なきゃいないで進んでいきそうなものだが、監督業は必ず設置される。
紅茶にしますか?コーヒーにしますか?と問われて、んーーじゃあコーヒーでとうのが監督の仕事だ。自分で飲むものを決めるのは別にどうということもないが、100人の客に出すコーヒーを決めるとなれば悩むこともある。
どの豆使いますか?ブラジル?コスタリカ?浅煎り?深煎り?とどんどん細分化していけばコーヒー出すにも幾つもの決断が必要になってくる。
フレーミングすること、切断することを担う役割というわけ。
昔の舞台芸術は劇作家が演出家を兼ねていた。
その役割が分業化されたのは19世紀後半らしい。意外と最近。
電気が出来たり、舞台表現が複雑化したのが理由ではないかと言われている。
決断を担う人間は色んなところに存在している。
どんな人間だろうと皆がそいつに決断を任せるとなったら、そいつは色んなことを決断していくわけだが、何にせよ決断する人間は必要とされているのは面白い。
人間の個人の決断だって、恋愛を他人(親とか)が決めていた時代は長かった。
いまだって他人の決断に身を委ねていることは山ほどある。
監督だって他人の決断に身を委ねたい時もある。
どっちでもいいよ、と私なんかはまあ放り投げてしまうこともしばしばだが、あとで文句言われたらやだななどど思われているかもしれない。
小さな決断も沢山あれば時間がかかるもので、監督が決めなくても良いのでは?というものまで判断しているといくら時間がっても足らない。
生きるか死ぬかがかかった決断をするとなったら、そりゃあ決断にも勇気が必要であろう。
アニメ作っている人が死ぬ、ということも滅多にない。
過労とかでスタッフが倒れないようには気をつけねばならないけど。
政治家は生き死にがかかった様な決断を迫られる場面もあるわけで、それはしんどいだろう。
しんどさに鈍感か、余程の使命感に駆られた人間だけが、その決断をになえるのかもしれない。
そんな決断をする人間を選ぶ決断をして投票箱に紙を滑り込ませる。
投稿者: 木村隆一
映画館へいきたい【2026年02月02日】
月末は1月二度目の行政がらみの会議。
会議といっても1時間半しかないので、各所報告とごく簡単な質疑応答のみで終わり。
久しぶりの知り合いに出会い、おーっと歓声を上げる。
寒さが戻って、外に出るのも面倒ではあるのだが面倒以前に仕事が終わらず家に篭りきり。
映画も一体いつから観ていないのやら。
近所の映画館にいくのすら憚られる。
春までは黙々と仕事をするしかないか。
ハサウェイは映画館で見ないと絶対見ない気がする。
暗いから。
SNSでは皆ハサウェイについて語っている。
しかも演出など技術的なことについて。
画がすごいのは、そうなのだろうけど。
とにかく映画館へは行きたい。
昔、渋谷にあったパンテオンで映画の上映前にラッパーのIce-Tが挨拶したいといって突然スクリーンの前に登場するという出来事に遭遇したのだが、いったい何の映画だったのかタイトルが思い出せずにいた。
ほんとにIce-Tだったのか?も怪しい記憶になりつつあったが、キアヌリーブス主演の「JM」を観に行った時に違いないと先ほど分かった。
彼が確かに出演しているし、パンテオンで見た記憶がある。
戸田奈津子が通訳で付き添っていた。
しかし、その時来ていた客はあの広いパンテオンに数人か、せいぜい十数人だった。
たぶんIce-Tのことを知っていた人もほとんどおらず、突然のアナウンスにも鈍い反応だったと記憶している。
詳しくは覚えていないが丁寧に感謝を述べ、さらっと去っていった。
なんだか申し訳ない様ないたたまれない気分になった。
客入りの悪さは映画の出来を考えれば致し方ないと思う。
マトリックス以外はパッとしなかったキアヌもあの頃の微妙な扱いに比べたら随分と人気が定着したし、おたく的な文化もキワモノではなくなった。
おたくは表に出られるようになった代わりに、オタク文化のアジールとしての機能は縮小している気はする。
日に当たりすぎるのも気をつけないと逃げ場を失う。
寒さは和らいで欲しい。
ラナンキュラス・ラックスの苗を買ったが寒さが落ち着くまでは植えるのを待つ。
雨が降らない【2026年01月24日】
年初からなんだかバタバタ。
2日にむぎを火葬して、行政絡みの会議やらもあり、レプリカは追い込み中。
動画協会の新年会では久しぶりの人に会えた。
年明けから約束していた人の作品のコンテに手をつける。
人の作品は気楽で楽しい。
なんかよくわからないけど仕事へのモチベーションは少し上がった。
植物もほったらかしだったが、枯れたセンニチコウとPWのユーフォルビアダイアモンドフロストを引っこ抜いてサントリーのウィンティーとローダンセマム・リルピンクを植えた。
黒っぽい花の咲くセージも。
しばらく雨が降っていないので2週間くらい?ジギタリスがぐったりしていて水をやる。
まさか夏越しした株なので春が楽しみ。
巨大になったアマリリスの球根の鉢が歪んでいるので春に咲く前に植え替えないとダメかもしれない。
いまいち育たない植物も他のものに入れ替えたい。
加藤一二三が亡くなった。
解散総選挙、だとか世界はもバタバタしてるがまあのんびりやろう。
アイキャッチ画像変えようと思って忘れていた。
ストリーボード作成で学ぶ演出(のための準備)【07】絶版ばかり…理論書
映画理論の歴史の流れがやっと分かってきた。
そもそもは1920年代、認知心理の学者らしいヒューゴー・ミュンスターバーグが書いた「映画劇――その心理学的研究」映画研究の嚆矢とされているようだ。
そのあと色んな研究がありつつ精神分析などと結びつきながら記号学的な方向へ収束していき、停滞。みたいなことらしい。
批評的な研究はずっと続いているけれど、実践と結び付けられそうな理論は80年代からそう変わっていないよう。
ミュスターバーグの論文が読みたいが、邦訳の載ったフィルムアート社の「映画理論集成」は絶版。
なんとか手に入れたい。昔はどこでも売っていたのだが…買っておけばよかった。
実践に使えそうなところとしては、認知科学的な理論と記号学的なものとアタリをつけていたものの、ごく初期が認知科学とは知らなかった。
ミュンスターバーグが、映画は観客の心に結像するのが最終形態、的なことを言っているらしく、納得。心的な現象として捉えていたらしい。その流れで精神分析と結びついていった様子。
ミュスターバーグは物語映画しか扱っていなかった、などの理由で批判されたりもしていたようだ。
そもそも心理学者なので映画論はあまり書いていない模様。
自分の趣向的にはアンドレ・バザン的な現実を映しとることが映画の最高みたいな方向に似ていると気づく。
エイゼンシュタインはモンタージュで現実を超えた何かが(ちょっと違うか?)立ち現れる的な世界観。
実質はエイゼンシュタインとバザンの中間あたりかな。
記号学的にはメッツの理論を押さえておけば、まあ大丈夫そう。
しかし絶版なので読めるか微妙。
水声社に在庫があるものもあったと思う。
間接的には浅沼圭司を押さえるしかないか。
浅沼圭司「映画のために」も絶版ぽいが…。水声社のオンラインショップに書影があるから一応まだ在庫を持っているのではないかという期待。
映画理論の流行ってい無さよ…。
「Film Art」という今も毎年更新されて出ているらしい映画の教科書は名古屋大学出版会から、しばらく前に出ていて、それはパラリとめくった。
初学者向けで映画制作全般にまつわる話題を網羅的に扱っている感じなので、良い本だが演出技術的なものは薄め。
まだちゃんと読んでいないが「VISUAL STORY」というボーンデジタル出版から出ている本は南カリフォルニア大学で教えている先生の構図とストーリーの関係について書いてあって比較的に面白そう。
東京大学出版会から出ている「映画論の冒険者たち」の著者がnoteで映画理論の重要本を70冊紹介していて参考になる。ミュンスターバーグにも触れられているのでこの本は読んだ方が良いかも。
正月に読もうと思った本が何も読めていない。
どこで読めるかな。
見送った【2025年12月31日】
むぎは土曜に病院に行って、1、2日持たないだろうと思っていたが驚異的な生命力で4日も生き延びた。
食事は病院に行く前の晩から何も食べておらず、ここ2日くらいは水もほとんど飲んでいなかった。
たまに注射器で入れてやった水を飲み下すくらいのものだった。
家に来た時は6歳くらいの推定年齢とのことだっが、先ほど保護主からの連絡で昔のカルテがでてきたらしい。
それによると2015年の生まれ、で10歳くらいだったようだ。
6歳にしてはしては少し鈍臭いと思っていたが納得した。
1本しかない歯はキュートだったが、多頭飼育していた老人の扱いの酷さが窺える。
家に来た当初は子猫の様におもちゃで遊んでいて、子供返りしていたようだ。
異様に人懐こく、老人が最後まで手放さなかったのも納得できる気がする。
むぎは老人の家を脱走し、飼い主を探し当てたところ多頭飼育崩壊の現場だったということらしい。
今日の昼間は比較的穏やかな顔をしていて、人の動きに顔を上げて見つめたりもしていた。なにせ人懐こい猫だったので、そこにいろ、ということだったのだろう。
逝ってしまう直前までは、なんだかこのままずっと居るのではないかと思ってしまうほどだった。
こちらの気持ちも少しは落ち着いて、いつものように接してみとってやれた様な気はする。
家の中は1年前にタイムスリップした様だが、むぎの爪痕はしっかり残っている。
前にも世話になった葬儀屋に大晦日の18時過ぎという時間帯に連絡してみたところ、1月2日から対応してくれるとのことで、助かった。
今はあまり実感も湧かないが、しばらくしたら喪失感がどっと押し寄せてきそうだ。
やろうと思っていた仕事はあまり進んでいないので、正月は年末に片付ける予定だったものを片付けねばならない。
ベテラン演出家が担当していたものを引き継いでいたものだが、基本的なことができていなくて唖然とする。
編集の時に気づけよという話なのだが、ベテランだし後で何とかするつもりなのかとタカを括っていた処もあり、非常に反省した。
とはいえベテランを叱責したりするのも嫌なものがあり、憂鬱。
むぎの病気を知る前日、voilの忘年会があり大高くんに参加せよと言われたので顔を出した。
久しぶりに若者とたくさん話して、というか社長大高くんに送り込まれて私のところへ来ていたのだが、皆なかなかのキラキラで前向きな若者たちで少し心が洗われた。
結構いい会社だな、voil。
年を越した感覚はない。
2026は仕事も心も空っぽ。
何かで満たせるだろうか。
イブはオールラッシュだった【2025年12月25日】
菊地成孔がSNSで書いてた文章が面白かった。
”音楽は、社会派であるとかないとか、理論理解があるとかないとかいう蒙昧な二元論のリージョンとは無関係に、そもそも全てが社会的な現象であり、理論的な現象であり、同時に、純粋な非社会性、超論理性を備えた存在ですので、好きな時に海から塩が採れるように、自由に社会問題や理論構築と結びつき、姿を変えることができる。”
全体は長文なのだが「自由に〜姿を変えることができる」について、はて、振り返って我が仕事のアニメはどうかと考えてみた。
そもそも映像は音楽ほど抽象化されていないので音楽と相対的に比べれば自由に姿を変えることは出来ないだろう。
もちろん抽象的な映像も存在するのだが、物語を扱う様なものは基本的に具象の世界だから。菊地の言っていることは、もっと幅広い意味を指しているのだろうけど。
アニメからも色んなことが汲み取ることができると思うが、今のところは掬い上げられているものは限定的に感じる。
作ってる方はもっぱら動物的なので、何が掬い出されているのか気に留めている気配はない。
掬い出されるか分からないそっと忍ばせるための旨味の様なものは、いつも考える。上手くやれていれば観客の嗅覚味覚を刺激してくれる。
アニメから何が掬い出されるのか、別に何も掬い出されなくても構わないが作り手としては受け手の中での変容をある程度見通せないと行き詰まるだろう。動物的な直感と世界の波に身を任せつつ。
アニメ業界のおじさんたちの体力は限界を迎えている様に見える。
自分を含めて。
幻想を形に落とし込むまでの体力がなくなってきている。
例外はもちろん沢山いると思うが。
若者がおじさんの尻拭いに忙殺されないように準備しないといけない。
いつもの授業【2025年12月22日】
週末は、毎年恒例になったDA-academy(声優向けのワークショップ)の授業。
いつも時間オーバーで駆け足になるので、抽象的な部分を少し省略して臨んだ。
結果的には、もう少し見直した方が良いか…と喋りながら考えた。
リアリティの話を演技に具体的に紐づけたのは、まとまって分かりやすくなっのだが、物語・フィクションの必要性や無意識の話をバサっと落としたので、若干膨らみを欠いてしまったかもしれない。
1時間で演出について話す、というのがそもそも難しいのだが重複する様な部分もあるので整理すればもう少し内容は詰め込めるかもしれない。
とくに無意識の話はあった方が良いかもしれない。
演技には凄く関係するから。
おまけのオーディションについての話が、一番反応がヴィヴィットだった。
それはそうだろうという気もするが、演出家がオーディションにおいて絶大な権限を持っている時代でも無いので、どの程度参考になったのかは分からない。
長い間そこそこ稼げるようになるといいのだが。
日曜は久しぶりに植物を買いに出かける。
ケイトウの寄せ植えがダメになったので、かわりを見繕う。
ストック、プリムラジュリアン、ネメシア、初雪カズラ、ワイヤープランツ、で作るつもり。
パンジー・ビオラも綺麗なものがたくさんあったのでつい幾つか買う。
植える鉢がないのだが。
あとはアネモネ極。
他にもアネモネは欲しかったが持って帰れないので断念。
ローダンセマム・サファリアイズがあったが、これも断念。
ほかにも幾つか欲しいものがあってキリがない。
とりあえず鉢を買わないと。
植物日記【2025年12月18日】
去年掘り上げた球根を植え付けていなかったので12月も過ぎてしまって、時期的には遅いけれど、しばらく前に植えた。
ムスカリは瓶の中で芽が伸びてしまっていて、取り出すにも一苦労だったが日があたってない芽が白いままで鉢に植えたあと更に赤みがでて、これはダメかもなと覚悟したがだんだん緑になってきて復活の兆し。
ムスカリは本当に強いんだなぁ。
アネモネは芽が出るまで、しばらく時間がかかると思うのでまだ分からない。
ヒヤシンスも瓶の中で芽が出ていたので、まあ大丈夫でしょう。
寄せ植えのケイトウが寒さで枯れかけなので、代わりを買いに行きたいが、いつ行けるのか…。
パンジー・ビオラかストックを植えるつもり。
春用の植物も良さげなのがあれば欲しい。
植える場所は後で考える。
トリツカレ男を見たり【2025年12月07日】
もう終わってしまいそうだったので火曜日の朝に「トリツカレ男」を見にいった。
脚本がロロの三浦直之、ということで見ておきたかった映画。
ボーイミーツガールだったり歌だったり、三浦直之的な要素はあるが、それほどロロっぽさは感じられなかった。
原作を手堅くまとめる方向で仕事をしたということかもしれない。
お話は、かわいくて好ましい。
ビジュアルも日本のアニメっぽくなくて、地味に凝ったことをやっており良い。
キャラクターデザイン荒川真嗣、レイアウト三原三千夫
美術はPablo。
美術は写実一辺倒の昨今に挑戦するのは非常に難しい作風をしっかりやり切っていて素晴らしかった。
作画と美術を上手く溶け合わせた背景動画的なシーンも結構あって、しっかり計画された画面構成だったのだと思う。
カラースクリプトなども作られていたのかもしれない。
キャラに質感を入れていたのがすごく印象的で、自分でも挑戦してみたいと思っている技法なのだけど、取り入れるのは難しい。
キャラクター造形との相性もあると思うが、かなり上手く処理されていた様に思う。
どういう方法で作られていたのか知りたい。
べたっとした色面にならない様にという意図なのだと思うが、漫画的な造形にも応用できないだろうか。
ミュージカルとしてのつくりは、もう少し頑張って欲しかった。
アメリカ、ヨーロッパの作品と比べると前半はかなり見劣りする。
ラストは良かった。
ミュージカルを作るのは、かなり大変。
脚本をつくり、ストーリーボードの前に音楽をつくるか、後に作るかの選択。
音楽も完成した状態のものを貰って作るのはかなり難しいのでスケジュールの調整だけでもなかなか難しい。
リップシンクは日本のアニメは伝統的にかなり大雑把なので、慣れてる人もいないと思う。
リップシンクそれそのものがエンターテイメントだった、という話は細馬宏通「ミッキーマウスはなぜ口笛を吹くのか」に詳しい。
トリツカレ男はミュージカルファンを当てこんだ作品というわけでは無さそうだけど、誰か挑戦したら面白いと思う。
トリツカレ男を見たあと、今日しかないと安彦良和展に足を伸ばした。
松濤美術館なので、それほど点数はないかと思っていたけど予想より多く資料が展示されていた。
ガンダムの作監修正(修正用紙に書かれていたが直接描いた原画なのかも)やポスターの原画の類が見られたのは良かった。
キャラ表のポーズは皆何かしらキャラクター性が分かる様なポーズがつけられているものが多かった。
今は造形を伝えることを主眼とするので、あまりポーズがつけられることはない。
キャラ表は色彩設計の色指定表としても使われるので、あまり大きなポーズをつけると造形が分からず色が作れないということが起こるからだ。
昔は色数も少なかったので、多少ポーズをつけたところで問題にならなかったのだろうし、ポーズがあった方がキャラクター性がアニメーターに伝わると考えられていたのだと思う。
確かに表情集は作るけれどポーズ集までは作られない。
本当は、あった方が良いのかもしれないが現状は手が回っていない。
安彦さんの絵はシンプルで、とても上手いのだけれど今風ではないのだというのは直筆の絵を見てあらためて感じた。
今風ではないというのは批判ではない。
特に目の作り。
今は目の中だけで異常な数の塗り分けがある作品が少なくない。
安彦キャラは目だけで惹きつける様な作りではない。
立体を意識しすぎず、ディフォルメもあってまさに2.5次元。
今はとにかく3D的に考えられがちなのとは対照的だ。
漫画のカラー原稿はとても魅力的だった。
塗りがとても美しくて、絵の具の滲みが綺麗に作られていてため息が出る。
昔のポスターなどは厚塗りで普通のポスターカラーかアクリルガッシュの様なもので描いていたのだろうか。
図録をみると展示されていないものも多数あり、他の会場では出ていたのだろう。
松濤でも展示替えがある様なので、多少は見られるかもしれない。
最近、精神分析について調べている流れでR・D・レインの「好き好き大好き」を読んだ。
エヴァのネタ本の一つらしいが、確かに似ている台詞回しがあり、「精神防禦盾」などのワードも出てくる。
全体的には60年台の前衛芸術的な雰囲気で、実際影響も与えていたのだろう。
現代詩だが、脚本の様な対話が多く使われているのは著者が精神分析かだからか。
懐かしいアングラを感じた。
あとはグリーフケア関係の本をちょろちょろ読み始めていて島薗進「ともに悲嘆を生きる」は読み始めたばかりだが面白い。
ムスカリやアネモネの球根が植えられていない。
流石にそろそろ植えないとまずいが、急に寒くなって億劫だ。
仕事も地味に打ち合わせが多く、結局週末しかデスクワークは大きく進まない。
ストリーボード作成で学ぶ演出(のための準備)【06】番外:小川哲「言語化するための小説思考」
映像技法ではないけれど、とても面白かったのと教える時に役立ちそうなのでメモ。
著者は技術書ハウツーの類の本ではないと言っているが、小説創作の過程がわかりやすく言語化されていて面白い。
1)小説刻の法律について
小説家も読者を意識する、した方が良いと言う話。
小説法に違反すると「駄作だ」「面白くない」とか言われるらしい。
SF、エンタメ、純文学、推理、などジャンルによって読者の読み方が違う。
誰に向けて書いているのか意識しないと批判されたり、伝わらない。
そもそも、自分と自分以外の小説の読み方、楽しみ方が違う。
自分が面白いと、読者が面白いのすり合わせが必要。
2)小説の勝利条件
将棋のAIによる形成判断が、小説にあったらどうか?と言う話。
小説には明確勝利条件が存在しないが、読者に面白いと思わせることと仮定して話が進む。
桃太郎を書くとしたら何処から書くか、将棋の手の選択のようにいくつかの選択肢の中から小説家がどの様な思考で選択肢を絞っていくかについて。
3)知らない世界について堂々と語る方法
世界の構造の抽象化と個別化
自分の知っている、あるいは調べた(聞いた)世界を抽象化して別の世界に置き換えて個別化すると言う話。
4)文体とは何か?
著者が文体においてもっとも重要だと考えている要素「情報の順番」の話。
「読みやすさ」とは「登場人物と読者の情報量の差を最小化する」ことではないか?
5)君はどこから来たのか、君は何者か、君はどこへ行くのか
新人賞の選考は「突然知らない人から話しかけられる」体験に近い、と言う話。
今されている話は、笑えるのか、怒っているのか…作家との文脈がないと分からない。
多くの人は行き先のわからない電車に乗っていると不安に感じるようだ。
新人作家は、作品がどこへ向かって何を与えるか(可能な限り)作品の序盤で明らかにした方が良い。
6)小説はコミュニケーションである
知人・友人との話は多くの事前情報を共有している。
読者とのコミュニケーションを円滑にするためには、適切の情報を与えなければいけない。
7)伏線は存在しない
読者はいつも展開を予想しながら読み進め、書き手は読者の予想を想像しながら展開を決めていく。
小説は伏線そのもの。
「展開を暗示すること」と「暗示されていない展開に対する違和感を減らすこと」の二つによって成立している。
8)なぜ僕の友人は小説が書けないのか
つまらないアイデアの2つのパターン。
「専門性が高すぎる」「陳腐すぎる」
「主張」や「設定」から発想しようとするのではなく「書いてみたいこと」や「考えてみたいこと」から考えてみた方が良いのでは?と言う話
9)アイデアの見つけ方
商業的に成功する人は「もともと読者(他者)の物差しを内面化している人」か「なるべく読者の物差しに合う様に、自分の物差しを調整した人」
読者の分析は非常に難しい、分析の質を上げるには「作品を発表すること」が一番近道なのではないか。
面白い小説に必要なのは「新しい情報」か「新しい視点」
アイデアは発想力やオリジナリティではなく見つけるものではないか?
10)小説ゾンビになってわかったこと
小説を探す上で最初に捨てないといけないもの=自分の価値観
価値観の相違の中に、まだみぬ小説がある…かもしれない
どれも極力具体的に語られていて、わかりやすい。
特に文体と順番の話は映像にとっても重要。