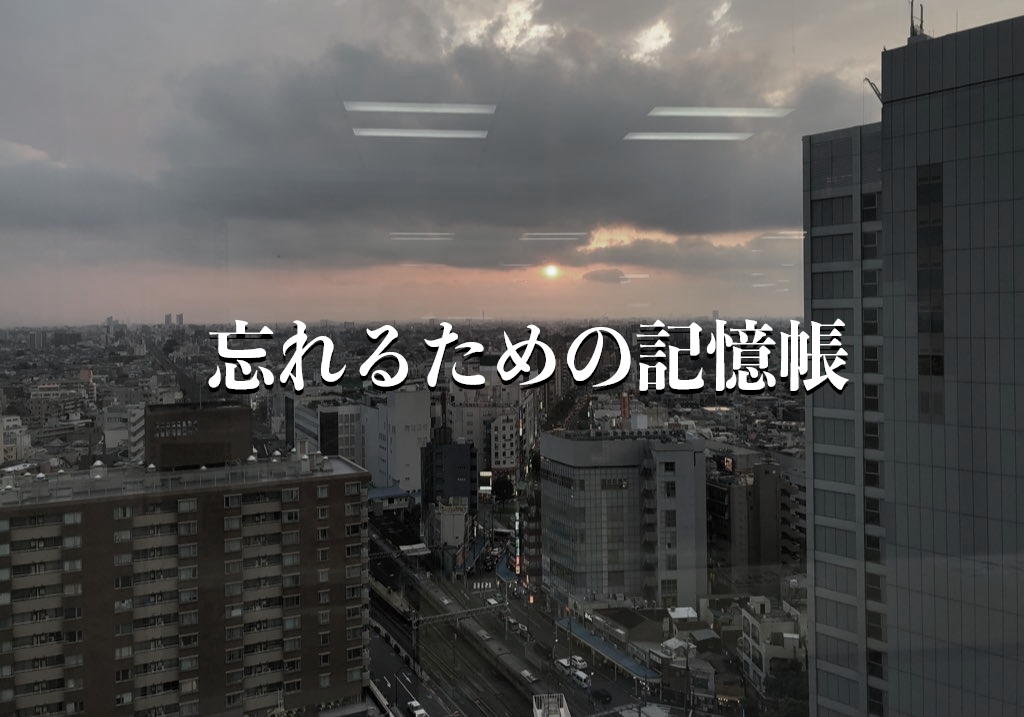いろいろ探してみたけれど一般書で出ている映画理論の入門的な本は殆どなくて、2000年に勁草書房から出たこの本くらいしか見当たらなかった。今も新しい刷りで売り続けてるので参考に良さそう。
映画理論講義 –映像の理解と探究のために
著者:
ジャック・オーモン
アラン・ベルガラ
ミシェル・マリー
マルク・ヴェルネ
訳者:
武田 潔
目次:
序論 …………………………………………………………………………………. 3
I 映画文献の分類 ……………………………………………………………… 5
1 “一般的な”の出版物 ……………………………………………………. 6
2 映画狂のための書物 ……………………………………………………. 7
3 理論的著作 ……………………………………………………………… 8
II 映画理論の諸相 ……………………………………………………………. 10
1 “内発的”理論 …………………………………………………………. 10
2 記述的理論 …………………………………………………………….. 11
3 映画理論と文学 ……………………………………………………….. 11
4 映画理論と技術的実践 ………………………………………………… 12
5 映画理論の多様性 ……………………………………………………. 12
注 ……………………………………………………………………………… 15
第1章 視聴覚的表象としての映画 ………………………………………….. 19
I 映画的空間 ……………………………………………………………….. 21
II 奥行きの技巧 …………………………………………………………….. 32
1 遠近法 …………………………………………………………………. 32
2 被写界深度 ……………………………………………………………. 35
III ショットの概念 ……………………………………………………………. 41
IV 聴覚的表象としての映画 ………………………………………………… 48
1 経済的=技術的要因とその歴史 ……………………………………… 48
2 美的およびイデオロギー的要因 ……………………………………… 49
注 ……………………………………………………………………………. 55
第2章 モンタージュ …………………………………………………………… 61
I モンタージュの原理 ………………………………………………………. 63
1 モンタージュの対象 …………………………………………………… 67
(1) 映画作品の一部分(映画的連辞)でショットよりも
大きいもの …………………………………………………………. 67
(2) 映画作品の一部分でショットよりも小さいもの …………………. 68
(3) 映画作品の一部分でショットへの分割と(完全には)
一致しないもの …………………………………………………… 69
II モンタージュの機能 ……………………………………………………… 76
1 経験的アプローチ ……………………………………………………. 76
2 より体系的な記述 ……………………………………………………. 78
(1) 「創造的」モンタージュ ………………………………………….. 79
(2) 統辞的機能 ………………………………………………………. 80
(3) 意味的機能 ………………………………………………………. 80
(4) リズム的機能 …………………………………………………….. 82
(5) モンタージュの分類法 …………………………………………… 83
III モンタージュのイデオロギー …………………………………………… 83
1 アンドレ・バザンと「透明性」の映画 …………………………………. 84
(1) 「禁じられたモンタージュ」 ………………………………………. 85
(2) 透明性 ……………………………………………………………. 87
(3) つながりのためではないモンタージュの拒否 ………………….. 91
2 セルゲイ・エイゼンシュテインと「映画の弁証法」 …………………. 92
(1) 断片と衝突 ………………………………………………………. 97
(2) モンタージュの概念の拡張 …………………………………….. 97
(3) 観客に対する影響 ………………………………………………. 97
注 ………………………………………………………………………….. 100
第3章 映画と物語 …………………………………………………………… 105
I 物語映画 ………………………………………………………………… 107
1 映画と物語の出会い ………………………………………………… 107
2 非物語映画――境界を定めることの難しさ ………………………. 109
(1) 物語的/非物語的 …………………………………………….. 109
(2) 境界の基準 …………………………………………………….. 109
3 物語映画――研究の対象と目的 …………………………………… 111
(1) 研究の対象 …………………………………………………….. 113
(2) 研究の目的 …………………………………………………….. 113
II フィクション映画 ………………………………………………………… 115
1 あらゆる映画はフィクション映画である ……………………………. 119
2 指向対象の問題 …………………………………………………….. 119
3 物語言表、物語叙述、物語世界 …………………………………… 121
第4章 映画と言語活動 …………………………………………………….. 187
I 映画言語 ………………………………………………………………… 189
1 古くからある概念 ……………………………………………………. 190
2 初期の理論家たち ………………………………………………….. 192
3 「映画の文法」 ………………………………………………………. 197
4 映画における言語活動についての古典的理論 …………………… 201
(1) 伝統的な映画言語 …………………………………………….. 202
(2) 言語活動の消滅に向けて? …………………………………… 203
5 記号なき言語活動 ………………………………………………….. 206
II 映画――言語か言語活動か? ………………………………………… 209
1 映画的言語活動と言語 …………………………………………….. 210
(1) 言語の多様性と映画言語の一律性 …………………………… 211
(2) 言語活動、コミュニケーション、極の入れ換え ……………….. 214
(3) 映画言語の類同的なレヴェル ………………………………… 215
(4) 線状性と離散的単位の存在 ………………………………….. 216
はい、続きをお送りします:
(5) 映画における分節の問題 ………………………………………. 216
2 映画の理解可能性 ………………………………………………….. 218
(1) 知覚的類同性 ………………………………………………….. 219
(2) 「質料的希釈のコード」 ………………………………………… 221
(3) 映画特有の記述形式の形象 ………………………………….. 223
III 映画的言語活動の不均質性 ………………………………………….. 228
1 表現素材 …………………………………………………………….. 228
2 記号学におけるコードの概念 ……………………………………… 230
3 映画に固有なコード ……………………………………………….. 232
4 映画に非固有なコード …………………………………………….. 235
IV 映画作品のテクスト分析 ………………………………………………. 237
1 「言語活動と映画」における「映画作品のテクスト」という概念 …… 238
2 実例――D・W・グリフィスの『イントレランス』
におけるテクストのシステム ……………………………………… 240
3 文学の記号学におけるテクストの概念 ……………………………. 242
4 テクスト分析の抑制性と理論的射程 ………………………………. 248
(1) テクスト分析の主要な特徴 ……………………………………. 248
(2) テクスト分析における具体的な困難 …………………………… 251
注 ………………………………………………………………………….. 259
結論 ………………………………………………………………………….. 351
注 ……………………………………………………………………………. 359
参考文献(I、II)……………………………………………………………. 363
用語対照表 …………………………………………………………………. 403
索引(人名、映画題名、事項)…………………………………………….. 417
訳者あとがき ……………………………………………………………….. 453
原書は初版が1983年、改訂が94年らしいので30年くらい前にフランスで出版されたらしい。
私が学生の頃なので参考で扱ってる映画も古いがまあ仕方ない。
少し読んでみたが凄く抽象的な部分はあるけど、使えそう。
映画評論はずいぶん沢山出ているし理論的な更新みたいなものは無いのか?と思うけど無いのかもしれない。
渡邊大輔が言ってることなんかは新しいと思うけど、入門としては必要ないのか…いやそうでもないような。
YouTubeはじめ映像メディアは様々広がっているので本当は更新されて良さそうだが。
学校などでは、どういう本を教科書で使っているのだろうか?
私が見つけられないだけで、良い本があるのかもしれない。
フィルムアート社から出ている入門書的なものは実務的だけど理論が薄そう。パラパラめくってみただけなんでわからないが。
認知科学とかも随分進んでいるので、その辺りを引いたものもありそうなものなのだが。
その辺を調べ出すと無限に時間がかかりそうなので躊躇してしまうが、多少はやらないとダメそうだ。
そのあたりは良さげな本のあたりがついてるので。
私が学生の時は、ほしのあきら「フィルムメイキング」を使ってた。本人が講師だからだが。
エイゼンシュタインの理論などは、ぱらぱら読んだけど流石に嘘でしょみたいな部分も多くて今素朴には読めない。
「映画理論講義」はそのへんもざっくり整理してあるみたい。とにかくざっくりでも読まないとなぁ…。
実務的なものは他にも良さげな本があるので、参考にしようと思う。最近の学生はそういうのを読んでるのかもしれない。
映画記号論的なものはだいぶ前に死滅してしまったようで、理論書は流行らなくなったのかも。
私が教わった浅沼圭二で終わってるぽい。
映画分析的な本は色々ある。
苦手な蓮實重彦もめくってみるべきなのかもしれないが。
私のやろうとしてることも、どちらかというと実務寄りだし。
久しぶりに更新。