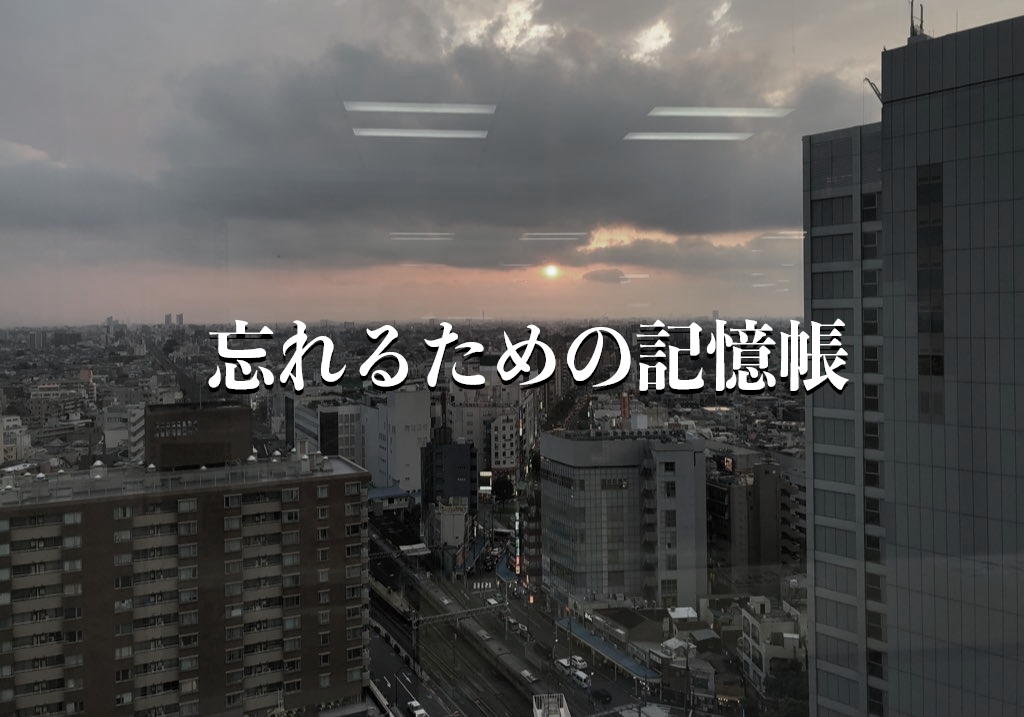そういえば、劇場版アイカツ!が今週末から再上映される。
もう劇場版初上映から10年だそうで、早いものだなぁと感慨に耽ってしまう。
土曜日には池袋のグランドシネマサンシャインで諸星すみれちゃんと舞台挨拶がある。
劇場版は結構たくさんイベントをやっていろんなことを喋ったので何を話そうかと考えている。
運営からの質問アイデアはあるものの何か話してないような思い出があったかな…と。
10年で随分いろんなことを忘れているので(何を話したかも忘れつつある)繰言のようなつまらない話にならないようにしたいものだが。
すみれちゃんが一緒にいるので、殆どの人は彼女を見るだけでも来た価値はあろうと思うのが救いである。
アイカツ!は定期的に昔を思い出す機会が訪れるので比較的に思い出せることは多いと思う。
当時、プロモーションで結構駆り出されて色んな事をさせられた記憶がある。
今も監督はプロモーションに寄与出来ているのだろうか…と甚だ疑問なことはあるのだが、体験としては面白かった。
今思えば、最初の頃は舞台挨拶も緊張していた。
初めての舞台挨拶は豊洲の劇場だったように思うが、控室では全く緊張を感じていなかったのだけれど、客前に出て急激に緊張したのを覚えている。
そりゃあ、結構大きなスクリーンだったし新人監督としては仕方ないだろう。
笑いの一つも取ってやろうと思っていたのだが、ジョニー役の保村さんがクルリと回って(控室では絶対パフォーマンスはやらないとか言っていた気がするが)華麗に笑いを取ったのを横目に見て感心するばかりだった。
大阪でも舞台挨拶とテレビ用のショートのインタビューとか。
告知を噛まずに言うのがいかに難しいか思い知った思い出がある。
コメンタリーなどのトークショーも凄くたくさんやった気がする。
殆ど私が司会進行のような形で90分のコメンタリー上映をやった時は流石に少し喋りが上手くなったような気分になれた。(大したこたぁないのだが)
何かの(アフレコだったか?)イベント終わりで予定していなかったスタッフが沢山参加してくれて助かった。
ただ喋るだけでも90分は非常に喉が疲れて大変なのだ。
そもそも、喋る内容などをある程度は考えておけば少しは上手く話せるのに、打ち上げの挨拶などですらその場の思いつきで喋ってしまう。
最近は良くも悪くも場慣れして緊張することもあまり無くなって上手くはないがリラックスして話せるので(トチっても気にしない)聞いてる方も楽しく聞いてもらえてると思っている。
一人でカメラに向かって話すようなコメント撮り的なものはいまだに苦手で、客前で話す方が気楽だ。
確か、バルト9でやった舞台挨拶の後、近くの交差点でファンの男の子が待っていてサインを求められた。
サインなど求められたことが無かったので普通に名前を書いただけだった。
アイカツ!に勇気づけられました、ありがとうございました的な事を言ってくれたのだが、ありがとうはこちらのセリフである。
この仕事をしていて、まさか誰かに感謝の言葉を貰う時が来ようなどとは思いもしていなかった。
子供向けであるし、素朴に面白ければ良いというつもりで作っていた作品なので、自分の想像を超えた反応に戸惑いというか申し訳ないような気分になったこともあるのだが、(何度も書いた気がするが)貴重なありがたい経験をさせてもらった。
劇場版は自分で絵コンテを描いているわけでもないし、演出もやっていないし、本当に周りのいろんな人の力で出来た作品だった。
自分の仕事のほとんどは、加藤さんとの脚本作りの中に集約されている。
当時の自分に出来ることや思いは全て投じて作った作品ではあるので、それが今だに多少なりとも人の心に残っているというのは嬉しい限りである。
久しぶりの劇場での上映なので、お時間のある方は是非見てほしい。
会える方は、土曜日に劇場で会いましょう。
タグ: 日記
猫・掃除・植物【2024年11月24日】
一番上の雄猫が旅立ってしまったので、我が家は女性上位時代に突入した。
メス猫2匹にオス猫1匹である。
長老メス猫は食欲も旺盛で動きも軽やか。下2匹との仲は、良いとは言えないのだが。
しばらくは元気でいてくれそうだ。
別に仕事が落ち着いたわけでもないけれど、一つミッションが終わったので突然部屋を片付けたくなって始めてしまった。
手っ取り早い掃除は「捨てる」だけれど捨てることすら忘れているものが結構あるので掘り出すところから始めることになる。(コンマリに拝礼)しかしどんどんエントロピーが増大するだけで途中差しのまま仕事に戻るに違いない。
年末なので家の中をひとしきり掃除したいけれども、果たしてどこまで出来るやら。
今週のオンライン編集は、えらく待ち時間が長くなってしまった。若い人と長々と話す機会も最近はそう多くないので、仕事は進まないがこういう時間は面白い。
元は現場にいた(私の現場にいたこともある)若いPがいて逆の立場になって悩むこともある、というようなことを言っていたのでそれは良いことで現場にいた経験が色々生きるんじゃない、と答えたのだが、まあ分かる気がするな思って聞いていた。
元現場にいて出版社やクライアント側に転職した人たちも最近は増えているようで、そういう人は現場との架け橋に実際なっていたり、なりそう。
出版社側から制作側に来る人は今は給与が違いすぎて、無さそうだが…。
逆が起こるようになったら面白いんだろうな。
しかし、KADOKAWAを SONYが買収する話も出ていることだし、そもそもSONYもKADOKAWAも制作現場を持っているし、ぐるぐると掻き混ぜられて後数年の間に大きく様変わりするのは間違いなさそう。
作られる作品は、どんなものになっていくのだろうか。
使いやすいクラウドサービスを探している。
スタジオと家で同じデータを触れるようにしたいのだが、今使っているicloudは同期が不安定で使いずらい。容量と値段はとってもお手頃なのだけど。
上手い同期の方法があればそれに越したことは無いのだが、調べても良い対処法は出てこない。
スタジオが大きなサーバーを用意してくれれば良いのだが…いや結局DROPBOXなどの方が手軽で使いやすいんだろうけど。
誰かお勧めを教えてほしい。
植物を色々買ったまま植え付けを出来ないでいる。
土も買って来なくてはいけないし、雨が降ったり寒かったりで放ってあったのだが、少しまた暖かくなったことだし今のうちに植え替えないと春まで放置しそうだ。
暖かい日があるうちに植え替えないと根が張ってくれないので今週あたりがラストチャンスかもしれない。
寒さに弱い植物も植え替えて冬越しさせるか悩ましい。
屋内に取り込めば冬越しできるのだけれど、玄関に置くにしてもまあまあ場所を取るので全部は難しそう。
しかし買ってきてから咲いている時間が短いものも結構あって、冬越しさせれば春からまた花が見られるものは越させて見たい。
プレクトランサスは、とても良く咲いたし掘り上げて鉢植えにして取り込むか。
五色唐辛子は元気ではあるけれど、あまり大きくなってないので、これも掘り上げるしかないのかも。
冬に強いものは、だいたい夏に弱い。
最近の凄い暑さを越えるのはかなり難しい。(とプロもYouTubeで話していた)
YouTubeには園芸関連のチャンネルが結構たくさんあって重宝する。
夏越しさせる方が冬越しより大変そう。
なるべく強そうな植物(=手がかからない)を選んで買っているのだが、しかし育てて見ないと分からないことはたくさんある。
PWのチョコレートコスモスは耐病性も上がった強健な種類ということで、しばらくは花上がりも良かったのだが、肥料を上げすぎたらしくうどんこ病に罹って一気に弱ってしまった。
肥料を上げた方が普通の花は花つきが良くなるのだが、肥料を上げるとうどんこ病に罹りやすくなるらしく(と、薔薇の育種家が話していて知った)またチョコレートコスモスはうどんこ病に罹りやすいようで、しくじった……というわけ。
手をかけない方が良いこともあるという学びを得た。
PWのアリッサムはセールで買った苗を夏に一回枯したのだが、秋に買った苗は順調に大きくなって植え替えた。
花芽も結構上がってきていて春には沢山咲いてくれそうな予感。
PW(Proven Winners)の植物は初心者が育てやすいものが多いのでつい欲しくなる。
巨大になるものもあって、どこに植えるのかは悩ましい。
次は何を買おうか?
ペットロス【2024年11月18日】
猫との別れは何度経験しても慣れないもので…。
具合が悪そうだな、と気付いてからあっという間に逝ってしまった。
4ヶ月ほど前の検査では、まずまずだったのだが、先週末ご飯を食べなくなって病院へ連れて行ったのだが。
膀胱の脇に腫瘍が出来ていたらしく、それが静脈を圧迫して歩行も難しくなっていた。
歩きづらそうだな、と思っていたが猫は痛みを我慢するので、そこまでクリティカルな原因があるとも思わずにいた。
腎臓の数値も悪くなっていて、しかしまだ何とかという所だったようなのだが腫瘍との相乗効果か急速に体調は悪化したようだ。
ここ最近の急な寒さで激変したのかもしれない。
まあまあ歳だったので仕方ないないと思うのだが、もう少し上手く対処してやれば楽に逝けたのかななどと詮無いことを考える。
しかし言葉の通じない猫の変化を素人が察知するというのは、なかなか難しい。経験を積めば重要な変化に気づけると思うのだけれど。
人間というか、自分自身のことですらままならないのだから。
ペット界隈の医療は二極化しているそうで、街のホームドクターと大学など専門機関。高度な医療を施すところは、とても高い医療費を取るらしい。
専門の機関だと検査で20〜30万、手術で40〜50万、合わせて100万くらいしてしまうとか。
確かに、前の猫で検査してもらった時は結構取られた記憶がある。
老齢の犬猫に高い手術をしたとて、そう長く寿命が伸びるわけでも無い事が殆どだろう。苦痛は取り除いてやりたいが、さすがに何処まで手をかけるか悩ましい。
もうしばらくはペットロスから抜けられなさそうだ。
もう11月も半ばを過ぎてしまった。
来年は頭からバタバタしそうだし、なんだか余裕がない。
とある原作者の人に、コンテの絵が綺麗で驚いた、というようなことを言われた。漫画のネームのようなものかと思っていたと。
まあ確かに漫画のネームよりはアニメの絵コンテは詳しく絵が描かれている事が多いかもしれない。
これは良し悪しがあって、そもそも絵コンテだって漫画のネームのようなかなりラフな絵でも問題がないはずだ。
ラフな絵ですめば、そちらの方が圧倒的に早く描ける。
漫画と違ってアニメは大勢の人間が関わるので下書きも他人が分かる絵である必要性が少し高い。
しかし、必要な情報が分かればそれほど丁寧に描く必要もないわけで、現状の絵コンテの几帳面さはアフレコが絵コンテを撮影した映像で行われるという場合があることへの対処という側面が強いように思う。
もちろん他にも(絵的に)詳細な絵コンテが描かれる理由はあるのだが、スピード重視で描かれる事があまりないのは、殆ど上記の理由ではないだろうか。
世の中には凄い人がいて頼んで10日もあれば詳細な絵が入った絵コンテが上がってくることもある。
しかし、それは稀で普通の人だと一本の絵コンテを上げるのに3週間から6週間くらいが平均だろう。(もちろん他の仕事もしながらのスケジュールなのだが)
ただ、ラフだけだったら2日3日で出来てしまうという人は少なくないのではなかろうか。
ラフだけ演出家が描いて、清書をアニメーターに任せるようなやり方も有りそうだが実際は殆ど例がないと思う。
絵コンテについては、もう少し効率的な方法が色々な形で模索できそうなのだが、なかなかそうはなっていない。
絵が綺麗だと褒められるのは嬉しいのだが、問題の多い工程でもある。
泣きつかれて急ぎの絵コンテをこなしたりアイカツ!のイベント用の仕事があったりと10月末から忙しくてしんどいが、あと半年くらいはこんなこんな感じなのかもしれない。
神経質な時代なのかも【2024年11月02日】
今週はへとへと。
仕事で気力も体力も失って本も読めない。
のだが、また細かい仕事が増えたりして果たして終わるのだろうか…。
今週は連休なのだなと、さきほど気づいた。
昔は連休も土日も関係なく仕事の連絡が来ていたりしたものだけれど、最近は大分少なくなって健全になったものだと思う。
急ぎの仕事の返信もまだ来ていないもの。
仕事でちょい驚いたことがあり、それにまつわることをメモ的に記す。
最近のアニメ制作は、ほとんどが原作ありきの仕事である。
最近でなくとも原作ものの仕事はずっとあったわけだけど揉め事などの話もよく聞いた。
しかし、お互いに歩み寄りやら色々あって、ここ10年くらいで作り方は非常に落ち着いてきているというのが個人的な印象。
もちろん今だに揉め事の話も聞いたりはする。アニメの話ではないけれど、ついこのあいだ原作者が亡くなってしまった事件まであったわけで。
しかし、トラブルシューティングなどは出版社など権利を持っている側と制作サイドともに随分とノウハウは蓄積されていて、穏やかに仕事が進んでいるところが多いのではなかろうか。
派手に揉めている話は随分聞かなくなった気がする。
あるいは揉めてもなんとかなる段階で手を打てているというべきか。
なんとかなる段階、それはプリプロ。
絵的には設定画などの確認。
お話は脚本の段階で、なるべくしっかり合意して揉めないようにしましょう、ということ。
特に脚本の擦り合わせは昨今非常に重要度を増している。
さて、過去アニメ業界ではシナリオを軽視する演出家も少なくなかった。
その理由は色々あると思われる。
ひとつはアニメに限らず映像化の際に原作を大幅に改変する場合があった。
もうひとつは、アニメオリジナルの作品が多かった。
映像化の際に原作を大幅に改変していた理由は色々あるのだろうけど、昔は改変がそれほど悪とされてはいなかった。
映像は別物としてあまり気にしない原作者も多かったと聞く。
もうひとつアニメにオリジナル作品が多かった頃は、演出家の裁量でお話をアレンジしてもそれほど問題にならなかった場合も多かったと思われ、そういう文化の中で育った人は、とくに悪気なくシナリオを軽視するということがあったのではないかという気がする。
実際、私もオリジナルの仕事の時は脚本に沿うことに凄く気を使うということはない。
といっても、シナリオを軽視しているわけではなく、映像化の際に必要なアレンジや、ノリでこの方が面白いかなといったアイデアを入れるときに凄く気を使はなくて済む、という程度である。
そもそも面白いお話を作るために脚本会議をやっているわけで、シナリオを無視して作るというのは、その時間を捨てるということなのだから馬鹿げている。
最近でもオリジナルの仕事で監督が勝手に話を変えて脚本家と揉める、という話も聞くことはあるのだが何故なのか…。
しかし昨今の原作もののシナリオは、少し繊細である。
シナリオ会議に原作者が参加する場合も少なくないので、意外に細かなところまで原作者の手が入っている場合がある。
脚本は原作サイドとの契約書にも似た機能を果たすようになっている。
なので、監督といえども簡単に改変はできない。
改変したければシナリオ会議の段階でアイデアを提案するのが筋なのである。
実際私も大きめの改変を提案することがあるが、それは会議の場で議論される。
各話のコンテマン、演出家はシナリオ会議での議論を知らないのでシナリオの改変は難しくなる。絵コンテなどは良くも悪くも極力シナリオに沿って描かれる。
とはいえ、脚本通りに映像を作るというのは無理なので映像化するために多少のアレンジはどうしても必要だ。
私が原作ものの各話の絵コンテを担当する場合も極力シナリオ通りに作って、明らかに変えた方が良さそうなところがある場合は、なるべく発注の段階で確認する。
描きながら分かったことは断り書きを入れて直すか、放置して監督に判断を任せるというのがもっぱらだ。
ノリで作って、それを面白がれた時代もあったのだと思うが、今は良くも悪くも難しい。
漫画にせよ小説にせよ原作もののお話は一人の人間が描いていることが多いので、どうしてもその人にしか分からない理屈のようなものでつながっている部分がある。
ブラックボックスのような、その人の頭の中だけにある理屈は創作の魅力にもなりうるものなのだけれど、映像のように大勢の人間が関わって作る創作物の場合は他人と共有できないと理屈そのものが抜け落ちてしまうこともある。
ブラックボックスはなるべく少ない方が良いし、しかしそれが無くなることも原理的にないと思う。
すくなくとも監督と共有できていれば作品が大きくずれたものになることはない。
しかし末端のスタッフの創作性や実務的な問題とどう両立させていくか、というのは悩ましい。
池田繁美さんが亡くなった。
夏色キセキの時に一緒に仕事をした。
ガッチリした分かりやすい設定が印象的だった。
昔気質の厳しい人であったのだと思うが、私は意外と気安く話してもらっていた気がする。
昭和の職人たちが亡くなっていくのは仕方ないことだが残念だ。
外れスキル<木の実マスター>【2024年10月26日】
1月から放送の「外れスキル木の実マスター」は「おとなりに銀河」の流れで大体同じようなチームで制作。
ファンタジーは各話の演出でも、ほとんど担当した記憶がない。外れスキルものが沢山あることも知らなかった。
お話は私世代なんかは懐かしくなるような王道の冒険ファンタジーで、とっつきやすく楽しく作れた。
原作チームも鷹揚でありがたかった。
制作の旭プロダクションは宮城の白石にスタジオがあって、そこのチームがとても優秀だ。
「魔法少女にあこがれて」の監督も務めた鈴木理人くん、演出の森あおいさん、おとなりに銀河のキャラクターデザイン大滝那佳さん、は白石のチーム出身で皆んな優秀。他の作画チームも優秀でびっくりする。
今回も参加してもらって、感心するばかりだった。これからどんどん活躍するに違いない。
メインキャラはアイカツ!でもう長い付き合いの宮谷里沙。忙しいところを無理に頼んで引き受けてもらった。
アニメ制作本数はスタッフの数に比べるとかなり多いので、どこのスタジオも苦労が多い昨今だが、若い優秀な人たちの仕事を間近で見る機会は楽しい。
若くなければ出来ない仕事はある。アニメ作りは意外と体力勝負なので、なるべく若いうちに良い仕事をする機会に恵まれると良いなと思う。
仕事の愚痴を書こうと思っていたけど、やめた。
2028年あたりの仕事まで決まっているとかいう話も聞くが、隔世の感がある。
果たしてこの先どんな作品がつくられるのだろうか。
暴力とアディクション【2024年10月21日】
最近読んだ本、信田さよ子「暴力とアディクション」
現代思想に書かれた短編の文章をまとめた本。大変面白い。
タイトル通り暴力とアディクション(中毒)が如何に関係しているかというテーマが主に取り上げられているが、そこには深く家族が関わっている。
信田のキャリアはアディクションから出発しているので、どちらかというとアディクションが先にあってそこに暴力がどう関わっているのか、という構図。
この本だけで沢山、物語のネタが出来そうな内容である。
アディクションの代表的なものとしてアルコールがある。
アル中への対処がアメリカで進んだのは、ベトナムからの帰還兵が沢山アル中になり、家庭の中で暴力を振るい、それが問題になったかららしい。
中毒は様々な社会問題と通底している、という具体例が様々示されている。
アルコール中毒に限らず、全ての中毒・依存症は自己治療的である、ということが随所で語られているのだが、これは普通の人間でも多かれ少なかれ思い当たることがあるだろう。
趣味でも仕事でも、のめり込んでいるもの・行為は自己治療的な側面がある。
それがなければ生存が危ういかどうかが依存症かそうで無いかの分水嶺だ。
中毒・依存症は本人にとっては治療的なので止めたくないが、周りが迷惑しているので止めさせたい、という構図が依存症治療の難しさらしい。
そりゃ大変だろう。
貧困、ジェンダー、家族、戦争、ありとあらゆるものが暴力・アディクションと関係していて、これは表立って取り上げるかどうかはともかくとしても、物語を作るとき考えるべき事象だという気はする。
仕事をしながら流し見していたNETFLIXのガンダム(CGのやつ)が面白かった。
ちゃんと戦争ドラマをやろうとしていて好感がもてる。
実際の戦争はもっとえげつないけれど、ライトにでも戦争について考える様な作品を作ろうとする姿勢はファーストガンダムと通じるものがあって好きだ。
一貫してガンダムを恐ろしいものとして描いているのだが、こういう描き方を許容できるのか、というのも少し驚いたし良いことだと思った。
引っ張っていたコンテを終わらせたが、わんこそばの様に次は控えている。
まあまあ出来は気に入っている。
作画がどれくらい頑張れるかはわからんけれど。
細々した仕事を今週は片付けなければいけない。
10月は、あと10日ある。
将棋の竜王戦も3局目が終わってしまった。
佐々木勇気が1勝あげて面白くなってきた。
毎年、竜王戦が始まるともう今年も終わりだなと思う。
来年は試練の年(別に辛いことをやるわけでは無いが)で慣れない仕事をやらねばならぬ。
なので、なるべく終わらせられることは全て今年のうちに終わらせてしまいたい。
しかし、先の仕事はさっぱり決まっておらず…まあこうやって何十年か生きてきたのだから何とかなるだろう、とこういう文章を書いているのも自己治療なんだろう。
そういえば、久しぶりに自分の仕事の告知が出たのを忘れていた。
ファンタジーをやるのは初めてだが、昔の少年漫画のようなノリの原作だし、気分的には楽しかった。
現場色々あって予想以上に大変ではあったのだが、今どき大変で無い現場ほとんどなかろう。
今アニメの制作スケジュールはとても伸びていて、12、3本のシリーズを作るのに丸々1年くらいかかるのは普通になってきている。
なので告知も全然できない。
次はいつになるのやら……。
植物いじり【2024年10月05日】
植物いじりが唯一の楽しみになりつつある今日この頃。
秋は園芸シーズンで花苗などがたくさん出回るのだけれど、植物によっては寒さが苦手なものもあり鑑賞期間がそれほど長くないものもある。
0℃を下回ったとき枯れないかどうかが分水嶺なのか、マイナス何度かまで耐えられるものなら冬越しできるみたいだ。1年草として、枯れるまで鑑賞するという花が沢山あるのだということを最近知った。
とはいえ、1月くらいまでは、そう寒くならないので大体の花は鑑賞できそう。
寒さに強い植物は、逆に暑さに弱くて夏に枯れてしまうものが多いらしい。
特に最近の夏の暑さ(今年はやばかったようだ)は暑さに強いものですら枯れてしまうこともあるという。
大体の花苗は大して高くなくて、無限に買ってしまいそうになるのだが、鉢が意外とお金がかかる。
焼き物などだと大きさにもよるが、そう気やすく買える値段でもない。
しかし全てを地植えできるほど広い庭があるわけでもないので、やはり鉢がメインになってしまう。
そもそも庭木を剪定するのに時期やらなんやら調べているうちに、園芸種の花に綺麗なものが沢山あることを知り、狭い庭でも工夫次第で意外と綺麗に育てたり飾ったりしている人がいることを知り、道を歩いているときに他人様の玄関先の植栽が目に入る様になり、上手な人は本当にオシャレに飾っているのが分かると真似をしたくなって園芸店に行ってみると楽しすぎて完全にハマってしまった。
園芸店はちょっと離れたところにあることが多くて車のない私は徒歩で運ぶしかなく一度にたくさん買えないのが残念なのだが、それでも毎日でも行きたくなってしまってグッと堪えている。
通販でも結構買えるのだが、やはりものを見て選ぶ楽しさは代え難い。
玄関先に死ぬほど鉢が置いてある(が管理しきれていない)家が結構あることに最近気づいたのだけれど、気持ちが非常に良く分かる。
大きな園芸店は大概郊外にあって車が無いととても行けないところが多い。しかし実は都心にも有名な園芸店の支店があったり、探すと意外に自宅の近くにもあったりして驚いた。
暇なら延々と巡りたい。
なんでこんなにハマっているのかよく分からないけれど、とにかく土を触っているだけでも楽しい。割とズボラでもそれなりに育ってくれる植物も沢山あって初心者でも意外にとっつきやすい。
最近気に入ったものはチョコレートコスモスでチョコレートの様な香りを発する。普通の品種は寒さに弱くて冬越ししないらしいが、改良されて頑張れば冬越しできる品種とのこと。冬を越えれば四季咲きとして楽しめるそうな。
冬は屋内に入れておけば大丈夫なのだけれど、寒さに弱い植物を全部中に入れていたらキリがないので、苦渋の選択を迫られるかもしれない…。
三人吉三、とエビデンスとか【2024年09月28日】
もう9月も残り2日。
今週はちまちま仕事とJAniCAの理事会があったり。
そういえば、いま「マンガ、アニメ、特撮、ゲーム等の国際的な振興拠点及びメディア芸術連携基盤等整備推進に関する検討会議」というのをやっている。申し込めば会議の様子をYouTubeを通じて動画で見られる。
博物館的なものを作ろうという計画があってその会議。
石破茂が自民党の総裁に決まったが、石破さんはオタクなので、もしかしたら本当に箱物が出来るのかもしれない。
緊縮であっさり無くなる可能性もあると思うが、実際できたとして他の分野はともかくアニメ・特撮は報いることができるのだろうか。
アニメは一応外貨を稼げそうな雰囲気はあるけれど、ほとんどの現場には今だに余裕のある予算は無いので疲弊して倒れるのとどっちが先かのチキンレースだ。
あ、週の頭はOTOの周年に行ったのだった。お祭り感があって久しぶりに楽しかった。
今日は木ノ下歌舞伎「三人吉三廓初買(さんにんきちさ くるわのはつがい)」を観劇。
間に休憩が25分、20分とあるけれど三幕5時間20分ほどの長丁場。
面白かったので、あっという間ではあったけれど、さすがに膝が少し痛い。
木ノ下歌舞伎は歌舞伎を現代語訳&現代的演出で見せるので素人でもとっつきやすい。
歌舞伎通の客も結構いるのだろうが。
最後はスタンディングオベーション、カーテンコール4回もやってくれたらそりゃ皆んな立つよね。
筋立ては、親の因果が子に報い、あらゆる登場人物が縁を結んでいることが徐々にわかり、それぞれ破滅を迎えていく。濃厚な親子の関係がモチーフになっていて重たいが重すぎて現実味がないというようにも思える話。
若い頃だったら嘘くさい様な気もしていたかもしれないが、今見るとシリアスでゾッとする。
家族というのは病の温床だが、さりとておかげで生きていけることもあるという厄介なものだという様なことをとある精神科医が話していたのを思い出したりもした。
鹿島茂は小説は結局、家族の話だけだというようなことを言っていた。
科学の発展で自然からはある程度距離を置いて生きることができる様になったものの、人間同士が距離を置くのは容易ではないよなー。
しかし、そんな重い話を外連味たっぷりに見せているからこそ、今でも人気の戯曲なのだろう。
ラストにかかる挿入歌はTaku Takahasi、ラップのリリックをロロの板橋駿谷がやっているのも面白い。
大脇幸志郎「なぜEBMは神格化されたのか・誰も教えなかったエビデンスに基づく医学の歴史」が面白そう。
本の紹介によると
エビデンスに基づく医学(EBM)という言葉が、あたかも医学が事実の裏付けのない空理空論からすでに脱却したかのような含みで語り交わされている。しかし、実際には医学における重要な判断にエビデンスが必須どころか努力目標としてすら求められていないという事実がある。
本書は、公衆衛生の発達、臨床医学の飽和、薬害事件による臨床試験の制度化などを背景として医学が統計技術を取り込んだ歴史や、EBMという言葉を考案した人物たちの来歴を紹介する。さらに、エビデンスについての誤解や拡大解釈から発展していくイメージとの相互作用に注目することで、医学が生産的に実証性を維持するための課題を探る。巻末に索引、用語解説、年表、主な登場人物一覧、医学雑誌歴代編集長一覧などを付する。
ということらしい。
エビデンス…と言われると弱いね。
大脇氏とシラスで対談していた松本俊彦氏の本も読んでみたいのだが…。
積読をもう少し解消してからか。
今週の積読消化。
だいぶ前に買っていた渡辺大輔「明るい映画、暗い映画」、藤山直樹「集中講義・精神分析(下)」
渡邊大輔氏の本は結構面白かった。
しかし、前半の批評は映画のための批評という感じで外側にあまり開かれていく感じがしなくて、そこは苦手。
後半の普通の映画評の方が面白い。
とくに鬼滅の刃については全く同意。
藤山直樹氏の方はフロイト以後の精神分析の歴史。本当にざっとさらっていく感じなので、興味のあるところは参考文献に上がっている本を読まないとよく分からない。
精神分析は実践がないと本を読んだだけでは何も分からない、と藤山直樹は言っているが。
精神分析には暇とお金がかかるので、無理じゃん?
精神医療は最近やっと少し理解できた気がするが、結構勉強しないとよく分からないし、イメージが掴みずらい。
いま?NHKで統合失調症に関するドラマがやっているけれど、精神科や心療内科は、外科・内科みたいなわかりやすさや親しみがない。
子供の頃から通い慣れてれば何となくイメージもつくのだが、そんなことはないので。
情報は探せば結構あるのだが、パッと感覚的に鷲掴みにすることは難しいし、1冊2冊、本を読んでも分からない気がする。なんとかならんもんか?
訃報・仕方ないのだが【2024年09月21日】
同世代の知人の訃報を聞く。
次の仕事で関わっていたので、そのうち会えるだろうと思っていたのだが突然の知らせに驚くほかない。
しばらく闘病していたとのことだった。
出会ったのはもう20年くらい前でお互いに新人だったが、彼は各所で活躍して気付けば立派な経営者になっていた。たまに仕事場が重なった時ににこやかに挨拶してくれたのを思い出す。
彼の会社が次の仕事に関わっていたので久しぶりに名前を聞いて会えるのを楽しみにしていたのだが。
50も過ぎれば人間いつ死んでも仕方ないよな、と思ったりはするのだが、残念だ。
今週はデスクワークと打ち合わせ幾つか。
STORYBOARD PROの新しいのをスタジオ用に導入したものの、WINDOWSに慣れていないなどありセッティングに時間がかかりそう。
生育旺盛で初心者でも育てやすいはずの植物を少し涼しくなったからと思って植え替えしたら、どうもそれが悪かったらしく急速に元気がなくなり枯れそう。
苗を見つけたらまた挑戦。
ちまちまと仕事、最近読んだ本【2024年09月16日】
9月頭、多少落ち着きはしたもののチェック物が絶えずやってきたり音響作業やら会議やらで地味に落ち着かない。
合間にコンテ作業もちまちまと。
立て込んでいるようだが、先のことはまるで決まっておらずで、どうしたものやら。
いつものことではあるのだが。
連休なことに気づかなかった。
祝日だから休みという仕事ではないので気にしていなかったのだが、最近は制作スタジオが休みをとること(建前的には)が多くなり、メールなどが減るので少し落ち着いたような錯覚を起こす。
YouTubeでBLUE SEEDというI.Gが制作のアニメを無料公開しているのを目にしてタイトルは知っているが見たことがなかったので頭の方を流し見してみた。
YouTubeはいろんな作品が無料公開されていて、作品によっては全話見られるものもある。
ひと昔前は無料公開なんてとんでもない、収益の損失だ!的な業界の空気だったのだが変われば変わるものだ。
商売の規模が大きくなったからこそ、こういった無料公開も可能になったということであるのかもしれないが。
それはともかくBLUE SEED、テレビアニメとは思えないクオリティである。少なくとも1話はビデオアニメのような完成度だ。スタッフもデザイナー・作監が黄瀬和哉だったりでI.Gのメインスタッフを突っ込んでいる感がある。
予算は、それほど出ていたとは思えないが…。
放映が94年の秋番組なのでエヴァの1年ほど前になろうか。
この頃のアニメ業界の隆盛を感じさせる。
制作がI.Gと葦プロが組んでいる。プロデューサーに下地さんの名前もあり、この辺りの縁で下地さんは葦プロを辞めI.GグループとしてXEBECを作ったということなのだろうか。
テレビの後のビデオシリーズはI.GとXEBECで作っているようだ。
今では絶対にCGを使うであろうヘリコプターやら車やら手描きでがっちりと描いてある。
*追記:初回でヒロインのスカートが破けパンツ一丁で逃げ回るという仕掛けに、のどかな時代を感じさせる。(女性客を基本的に相手にしていないということだ。今でもエロはあるのだが、この作品は今だったら特に男性向けに限定されることはない気はする)
ほんとにすごい。メカカットは1カット1万円くらいは出ていたのだろうか。
当時のテレビの平均的な1カットの単価は3500円くらいだと思う。
3500円………正直、私が仕事を始めて単価を知った時は衝撃を受けた。
バブルは弾けたとはいえ、世の中にはまだまだ金はあったはずで、なんでこんなアホみたいな安い値段で作ってるんだと思ったものだが(バブル真っ最中も安い値段で作っていたんだろうし)今、どのくらい変わったのかというと、まあだいぶマシになったとは思うのだが、まだまだである。
ダンピングでたくさん売って儲ける昭和の商売みたいな状況は長らく続いていた。
今は外貨が業界を支えているので、安くはあるが随分制作費は上がった。
話が横に逸れたが、90年代あたりまで、今では金をかけたとて出来ないようなクオリティのアニメがかつてはあった。ほんとに何であんなものが作れていたのか不思議というような作品がある。
ほとんどは若さが支えていたと思う。
しかし、若さは失われた。
今もまた、すごいアニメは作られているが、昔よりは格段にしっかり金をかけて作っているように思う。
金があるだけではクオリティは上げられないのだが、制作会社によっては人材を育てたり集めたりを頑張っていてすごい作品ができている。
一方、中堅の会社は苦労している印象ではあるのだが。
明石市が作ったという、市の歴史を語るアニメ「明石と時のこどもたち」もYouTubeで見られるのだが(小黒さんが紹介していて知った)91年制作、制作会社は亜細亜堂。芝山さんが監督で柳田さんが作監でメカなどは出てこないが、びっくりするような出来だ。
時代の豊かさを感じる。
とめどなく色々書いてしまいそうなのでこの辺で。
最近読んだ本、東畑開人「雨の日の心理学」素人向けにカウンセリングの技術を噛み砕いたという本だが具体的で比較的わかりやすい。東畑の他の本に書いてある内容と被るところもあるが、まとまりとしてはこれが一番まとまっているのかもしれない。広い意味で誰かの手助けをしている、あるいは手助けを必要としている人がそばにいるような人にはお薦めだし、介護や子育てで疲れている人にも役立つという気がする。
積読が過ぎるので、何とか解消したい。
机の横に積んである本をパラパラ読むと面白いものが沢山あるのだが、放置してあるもの多数。
信田さよ子が初めて本を出したのが50過ぎてからとか、私も頑張って小説でも書こうか…。