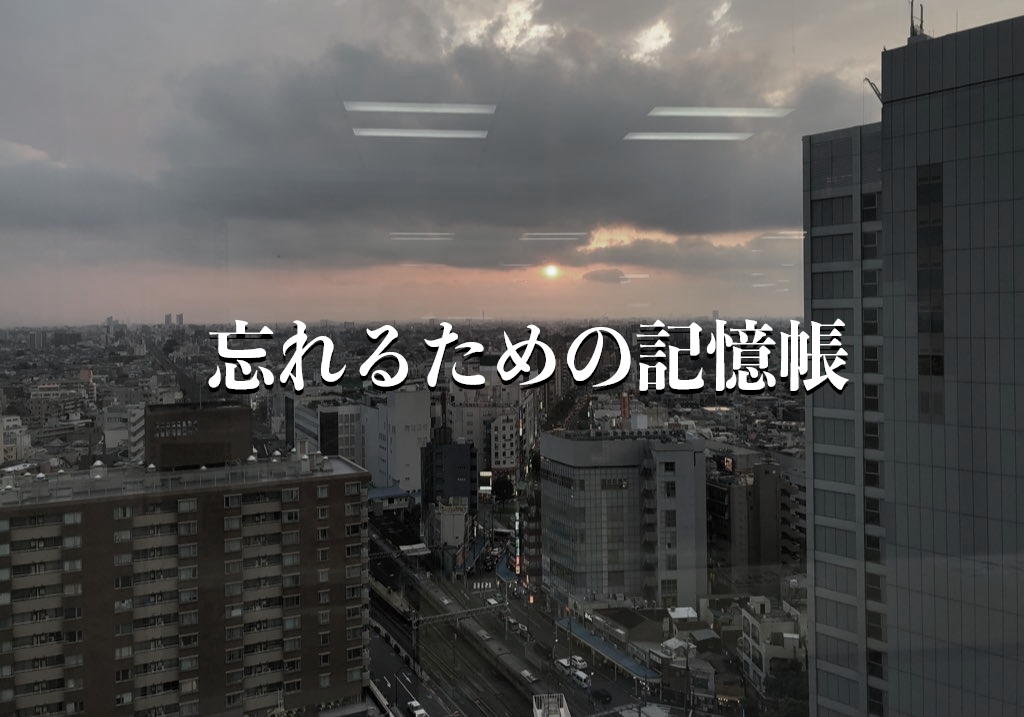もう終わってしまいそうだったので火曜日の朝に「トリツカレ男」を見にいった。
脚本がロロの三浦直之、ということで見ておきたかった映画。
ボーイミーツガールだったり歌だったり、三浦直之的な要素はあるが、それほどロロっぽさは感じられなかった。
原作を手堅くまとめる方向で仕事をしたということかもしれない。
お話は、かわいくて好ましい。
ビジュアルも日本のアニメっぽくなくて、地味に凝ったことをやっており良い。
キャラクターデザイン荒川真嗣、レイアウト三原三千夫
美術はPablo。
美術は写実一辺倒の昨今に挑戦するのは非常に難しい作風をしっかりやり切っていて素晴らしかった。
作画と美術を上手く溶け合わせた背景動画的なシーンも結構あって、しっかり計画された画面構成だったのだと思う。
カラースクリプトなども作られていたのかもしれない。
キャラに質感を入れていたのがすごく印象的で、自分でも挑戦してみたいと思っている技法なのだけど、取り入れるのは難しい。
キャラクター造形との相性もあると思うが、かなり上手く処理されていた様に思う。
どういう方法で作られていたのか知りたい。
べたっとした色面にならない様にという意図なのだと思うが、漫画的な造形にも応用できないだろうか。
ミュージカルとしてのつくりは、もう少し頑張って欲しかった。
アメリカ、ヨーロッパの作品と比べると前半はかなり見劣りする。
ラストは良かった。
ミュージカルを作るのは、かなり大変。
脚本をつくり、ストーリーボードの前に音楽をつくるか、後に作るかの選択。
音楽も完成した状態のものを貰って作るのはかなり難しいのでスケジュールの調整だけでもなかなか難しい。
リップシンクは日本のアニメは伝統的にかなり大雑把なので、慣れてる人もいないと思う。
リップシンクそれそのものがエンターテイメントだった、という話は細馬宏通「ミッキーマウスはなぜ口笛を吹くのか」に詳しい。
トリツカレ男はミュージカルファンを当てこんだ作品というわけでは無さそうだけど、誰か挑戦したら面白いと思う。
トリツカレ男を見たあと、今日しかないと安彦良和展に足を伸ばした。
松濤美術館なので、それほど点数はないかと思っていたけど予想より多く資料が展示されていた。
ガンダムの作監修正(修正用紙に書かれていたが直接描いた原画なのかも)やポスターの原画の類が見られたのは良かった。
キャラ表のポーズは皆何かしらキャラクター性が分かる様なポーズがつけられているものが多かった。
今は造形を伝えることを主眼とするので、あまりポーズがつけられることはない。
キャラ表は色彩設計の色指定表としても使われるので、あまり大きなポーズをつけると造形が分からず色が作れないということが起こるからだ。
昔は色数も少なかったので、多少ポーズをつけたところで問題にならなかったのだろうし、ポーズがあった方がキャラクター性がアニメーターに伝わると考えられていたのだと思う。
確かに表情集は作るけれどポーズ集までは作られない。
本当は、あった方が良いのかもしれないが現状は手が回っていない。
安彦さんの絵はシンプルで、とても上手いのだけれど今風ではないのだというのは直筆の絵を見てあらためて感じた。
今風ではないというのは批判ではない。
特に目の作り。
今は目の中だけで異常な数の塗り分けがある作品が少なくない。
安彦キャラは目だけで惹きつける様な作りではない。
立体を意識しすぎず、ディフォルメもあってまさに2.5次元。
今はとにかく3D的に考えられがちなのとは対照的だ。
漫画のカラー原稿はとても魅力的だった。
塗りがとても美しくて、絵の具の滲みが綺麗に作られていてため息が出る。
昔のポスターなどは厚塗りで普通のポスターカラーかアクリルガッシュの様なもので描いていたのだろうか。
図録をみると展示されていないものも多数あり、他の会場では出ていたのだろう。
松濤でも展示替えがある様なので、多少は見られるかもしれない。
最近、精神分析について調べている流れでR・D・レインの「好き好き大好き」を読んだ。
エヴァのネタ本の一つらしいが、確かに似ている台詞回しがあり、「精神防禦盾」などのワードも出てくる。
全体的には60年台の前衛芸術的な雰囲気で、実際影響も与えていたのだろう。
現代詩だが、脚本の様な対話が多く使われているのは著者が精神分析かだからか。
懐かしいアングラを感じた。
あとはグリーフケア関係の本をちょろちょろ読み始めていて島薗進「ともに悲嘆を生きる」は読み始めたばかりだが面白い。
ムスカリやアネモネの球根が植えられていない。
流石にそろそろ植えないとまずいが、急に寒くなって億劫だ。
仕事も地味に打ち合わせが多く、結局週末しかデスクワークは大きく進まない。