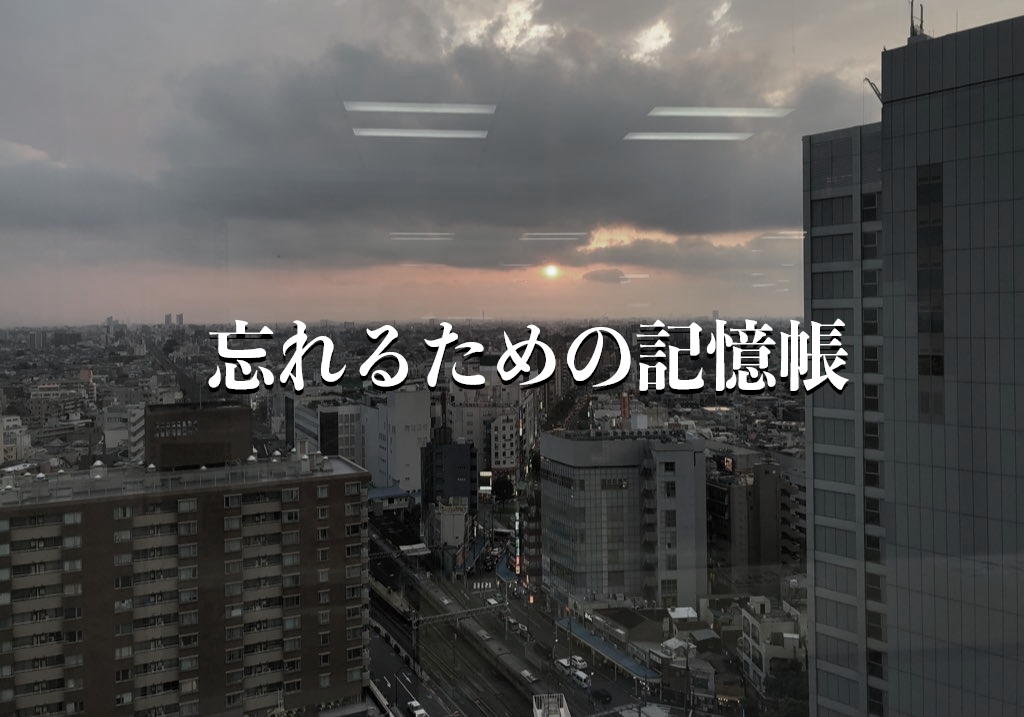SNSでぼっち・ざ・ろっくの脚本家の講演録が炎上していた、ようだ。
脚本家が原作の一部をノイズ(記事のタイトルにも使われた)として削除した、という部分に食いつかれていた。
そのノイズというのが性的表現に関するもので、余計に火種となったのだろう。
脚本家が原作の当該部分をノイズと判断した、という受け取られをしていたが、発案が脚本家だったにせよ、原作者も含めた会議体が判断したのは本文を読めば明らか。
延焼したのは知念実希人という小説家とくりした善行という元国会議員が参戦したからだろうか。
炎上させている輩は、インタビューを読んでいないか読んでいても読めていないか、倫理が欠如しているかという、ところなのであまり興味はないのだが、くりした善行のポスト(しかも英語の)中になるべく原作通りに作ってもらいたい、という趣旨の発言があったのは引っかかった。
漫画であれ小説であれ、アニメ化ドラマ化の際に原作通りである、というのはどういうことなのだろうか。
原理主義的に言えば原作は原作そのものであって、原作通りとは原作を翻案しないということに他ならない。
メディアを移せば様々な形態の変容を余儀なくされるのが翻案だ。
アニメで言えば、テレビシリーズであれば1話20分、12か13本のフォーマットに起こすのが主流になっている。
そもそも漫画、小説は時間を持っていない。映像は時間が物理の時間が流れ、決定的な役割をする。
漫画の場合であれば、2〜3話数くらいがアニメ1話分時間を有するという場合が多い気がする(作品によって違う)
この段階で、原作と印象が変わるのは間違いない。
どこで1話が終わるのか、というのは必ず頭を悩ませられる問題で、映像の時間に換えると中途半端なところで話が終わってしまう、あるいは長すぎるということが起こる場合は少なくない。
そうすると、追加部分を作る、あるいは削除するということになる。
もうこれだけで、原作通り、など不可能。
削除、追加はメディアが変わる以上は避けて通れない。
しかし、可能な限り原作通り、という風潮は制作現場全体にある。
特に最近は。
何のためにアニメ化するのか、基本は金のため、で高邁な原作をより世間に知らしめるため、などということは殆どない。
売れている原作は、良くできている、ものが殆どなので金を追求することがつまらないものを作ることにならない場合が多く、儲かる作品を翻案することは良い作品を作ることと意外と矛盾しないことは多い。
しかし、翻案するということは原作が形を変えることなのであって、原作者が換える先の形について詳しいなどということは無い。
詳しいなら原作者がアニメ監督、映画監督になれば良い。
原作者が監督したところで原作通り、にはなり得ないのだが。
アニメ制作は翻案する意味を宙吊りにしたまま、作品をつくることが多くなってしまっていると思う。
数打ちゃ当たる、という方針だ。
それだけの数の作品に投資できる様になっているのは凄いことではあるのだが、なぜアニメ化?と疑問符が浮かぶ作品も多々あることは間違いない。
翻案の方法についてもあまり深くは考えられていない。
そして、今の様なやり方の翻案ばかりではアニメの作り手の技量が落ちていくのは間違いない。