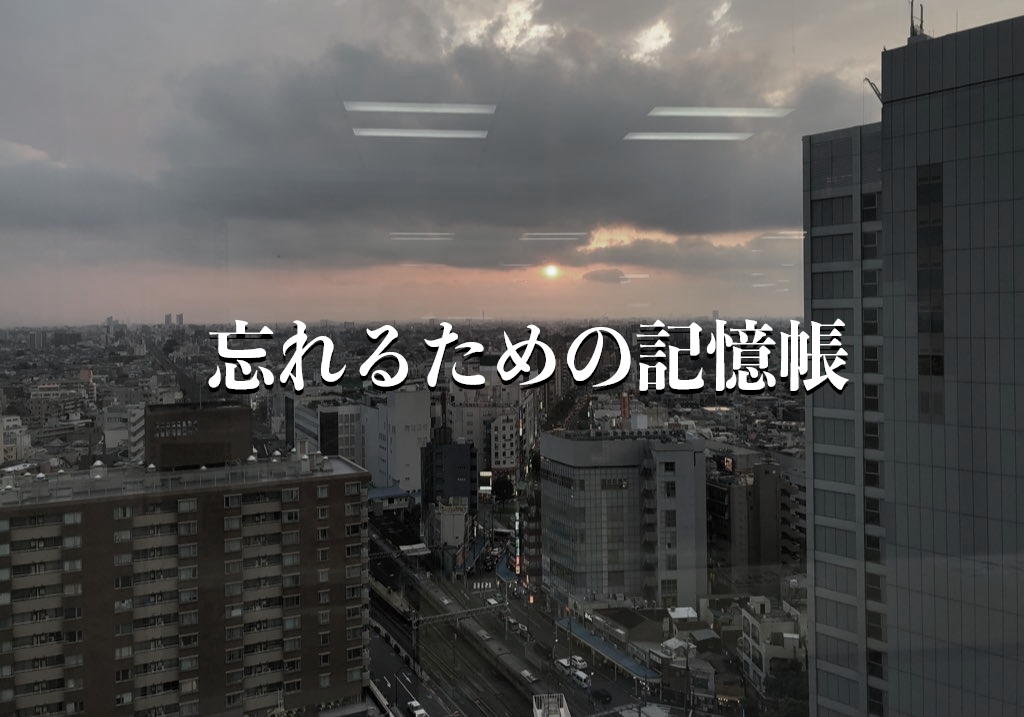絶対に洗濯したいものがある、という時に限って洗濯機は壊れるは激しく雨が降るは…でなんでかなぁと思わなくはないが世界はそういうもんだよな。
猫たちは仕事をし始めると構え構えと叫び出すが、いざ遊んでやろうと猫じゃらしを持つと寝始めたりする。
今も横で三毛猫が鳴いている。
梅雨があんまりなかったから雨が降るのは歓迎だ。尋常でない暑さを少々和らげてくれた。
買っておいた葡萄を夕食のあと食べる。
食事の後だと一房食べるのは、さすがに重く…しかし全て平らげてしまい、猛烈な眠気に襲われてしまう。
食べるととにかく眠くなるというのは、まあ健康なのだろうか。
胃に血流が集中して脳味噌に回している余裕がないわけだが、血液が仕事を終えると脳も活動の許しを得るわけで変な時間に目が覚めたりすることになる。
お酒を飲んで何かを食べるとしばらくするうちに必ず眠くなるので、よく寝ているところを写真に撮られて見せられる。
まあしかしお酒を飲んで食べるという快楽を半減させるのはしのびないので、食べてしまうし、眠くもなる。
先日、何となく眠れなかったのビールを飲んでいて何となく映画が見たくてAmazonプライムで新藤兼人の「濹東奇譚」を見た。
昭和初期あたりから戦後くらいの話で正面切ってはあまり出てこないが戦争の影を描いていて、今興味のあるところと重なる。
ウクライナの戦争を見ていて何となくウクライナ関係の本を読んだり、辻田真佐憲「戦前の正体」、宮崎駿「君はどう生きるか」とかたまたま戦争について考えることが多かった、夏だからというのもある。
中公新書の「物語 ウクライナの歴史 ヨーロッパ最後の大国」黒川祐次 著は、独立前のウクライナを知るのにとても良い。
濹東奇譚は、戦前の価値観みたいなものが老いていく荷風に重ねられて荷風が老いを認めて女を諦めていく様がとても良い。
濹東奇譚は売りはエロだったのだろうと思うが、大島渚の愛のコリーダと比べると愛のコリーダの方が圧倒的に華やかだ。
しかし濹東奇譚の方が何とも言えない情感が描かれている。
お雪の女優さん、墨田ユキがとても良い。
老いを描いている作品は若い頃見ても全くピンとこなかったが、今は実感と共に分かる様になった。
老いについてはともかく、戦争については、もうしばらく考えたり調べたりすると思う。