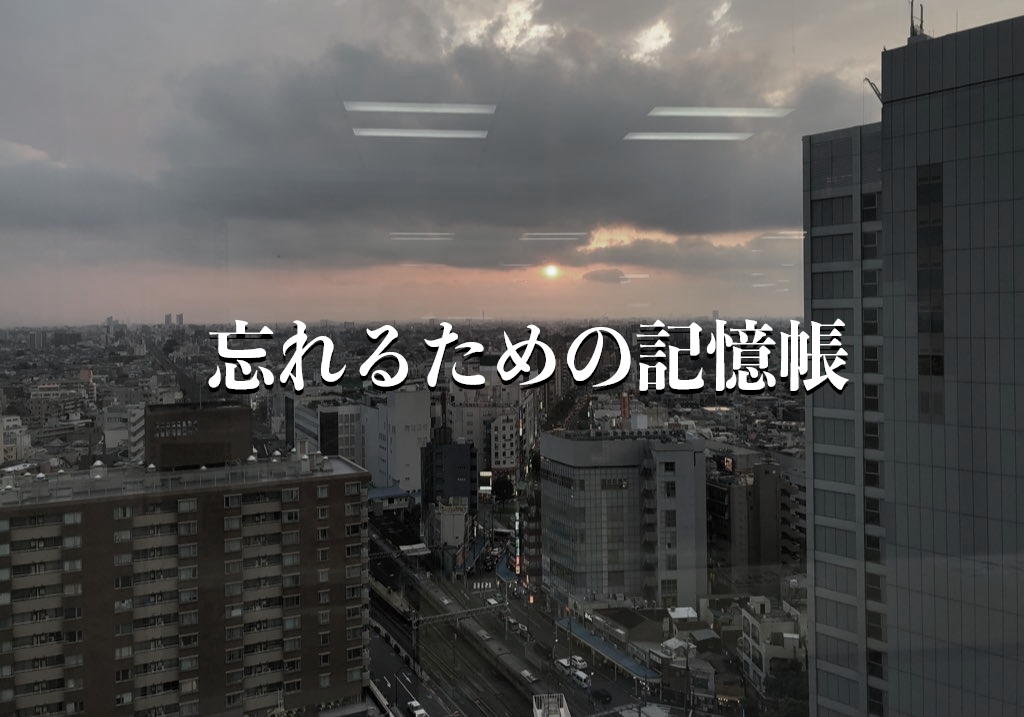あたたかくなったと思ったらまた冷えてチューベローズの植え替えをいつやろうか若干悩ましい。
今週は美術の打ち合わせがあって、その時に私が求めた絵画的な表現について、不安というかイメージが掴めないようで、しばらく自分の意図を話すなどした。
キャラクターのリアリティーに関わらず、背景はフォトリアルという表現は今のスタンダードだが、特徴的なのは目の大きいキャラクターとの取り合わせ。
フォトリアルな背景がメジャーになったのは押井守がパトレイバーで写真を下敷きにした背景に比較的リアルなキャラクターを上に置くことでリアリティーを作ったというあたりだろう。
キャラクターはカワイイが背景はリアル、という形式の嚆矢は、けいおんだろう。
今はどちらかというと、けいおんの流れが主流を占めている気がする。
キャラクターの抽象度は高く目が大きくてカワイイ、リアルな背景とは合わなさそうなキャラクターを組み合わせる、そのやり方は不気味の谷のようなものを感じてしまって苦手だ。
しかし、そういう表現の作品は山ほどあるし受けているので、何故そういう形式が求められているのかは考えている。
自分の作品では、比較的リアルめなキャラクターでも背景に絵画的なテクスチャーなどをなるべく残すようにしてもらっている。
背景がフィクションである事を担保してくれることが重要だと思っている。
ただ最近は背景の抽象度を上げるのは結構難しい。
抽象性の高いイメージを大勢のスタッフ間で共有していく難易度が高いからだ。
とくに透視図法を使わない背景はほぼ作れない。
透視図法は実は比較的簡単に共有可能な方法だ。
今フォトリアルな背景が席巻している理由の一つでもある。
3Dモデルを使えば余計簡単に透視図法のクオリティーは上げられる。
という事で、最近の背景美術の抽象度を上げるには、もっぱら質感ということになる。
テクスチャーは様々使えるようになってきているので、それなりに幅のある表現は出来るのだけど、作品ごとの決定的な差別化を図るのは難しい。
毎度悩むのだが、担当するスタジオやスタッフの持つ技術に大きく依存するので、そこで出来る枠組みの中で選択する。
3Dモデルを使うことに付随する問題も議論されている。
実写の撮影などを見たことがあれば簡単にわかることなのだが、狭い部屋のモデルなどでキャラクターを大きく映す時、かなり広角で撮ってしまうオペレーターがいるが、これはカメラの後ろの壁を外して引きじりを作れば簡単に解消できる。
そもそもレンズの選び方の意図が分かっていないとか。
アニメーターはアニメーターで透視図法が全く分かっていない人もいるし。
色々悩ましい時代ではある。